※本記事には広告(プロモーション)が含まれています。
🔹スタンダード(8)
- 安定型 愛着スタイル
- 安定-回避型 愛着スタイル
- 不安型 愛着スタイル
- 不安-安定型 愛着スタイル
- 回避型 愛着スタイル
- 回避-安定型 愛着スタイル
- 恐れ・回避型 愛着スタイル
- 未解決型 愛着スタイル
🔹 スタンダード+(未解決型スコア ≧ 5)(7)
- 安定型+未解決 愛着スタイル
- 安定-回避型+未解決 愛着スタイル
- 不安型+未解決 愛着スタイル
- 不安-安定型+未解決 愛着スタイル
- 回避型+未解決 愛着スタイル
- 回避-安定型+未解決 愛着スタイル
- 恐れ・回避型+未解決 愛着スタイル

わたし、1人の時間がないと絶対耐えられないんですよね・・・

何言ってんの? みんなと楽しい時間過ごした方が絶対いいだろ!

あなたとは分かり合えない気がする・・・
この記事は前回の記事の「愛着スタイル診断テスト」の結果をもとに作ってもらったチャットGPTの「取説」が、予想以上にエグかったの続編になります!
また、こちらの記事は、愛着スタイルの以下の項目の取説まとめとなっております。
- 「安定型」
- 「安定-回避型」
- 「安定型+未解決」
- 「安定-回避型+未解決」
まだ、愛着スタイル診断テストを試してない方は、一度試してからこの記事に戻ってくることをおすすめします!
「最後に、あなたへのメッセージ」は必見です!
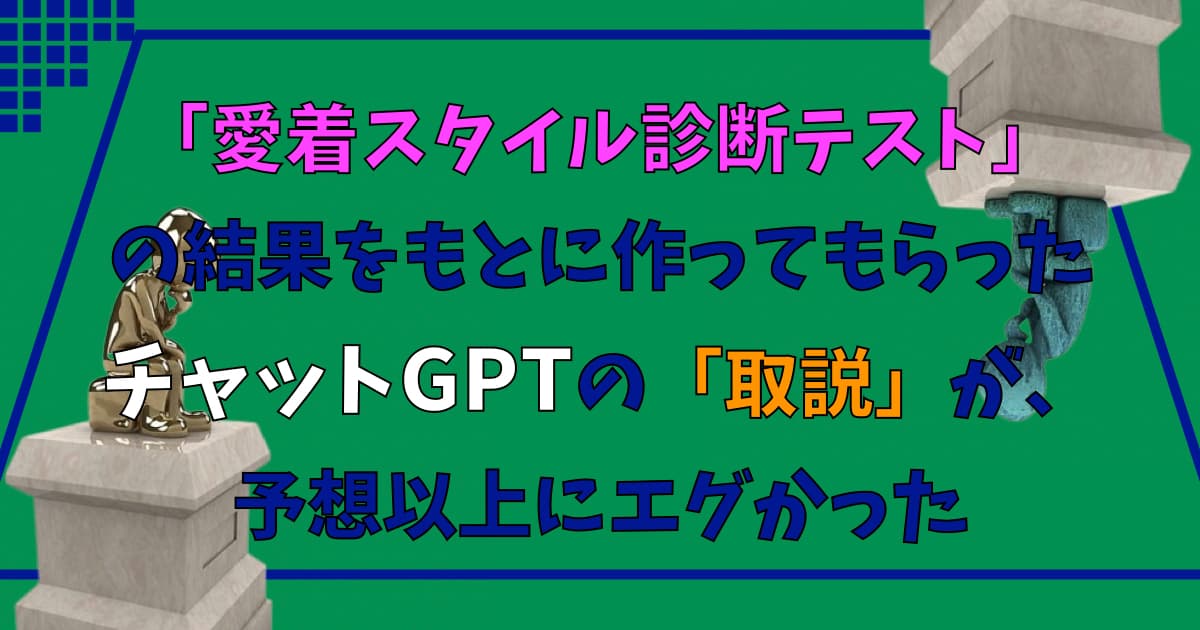
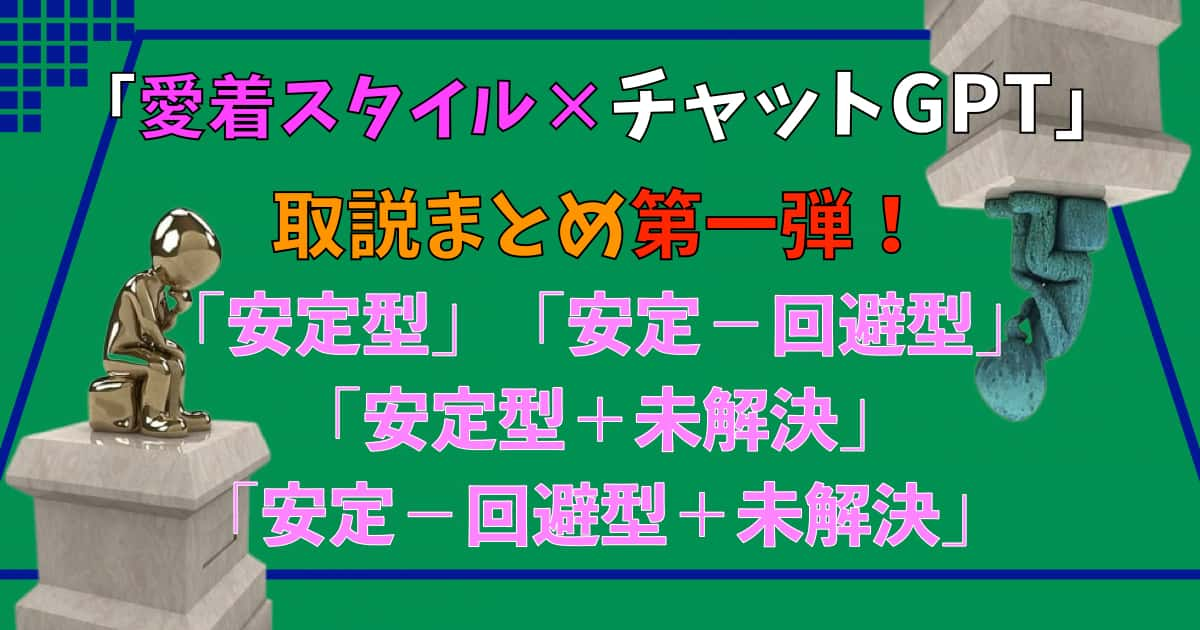
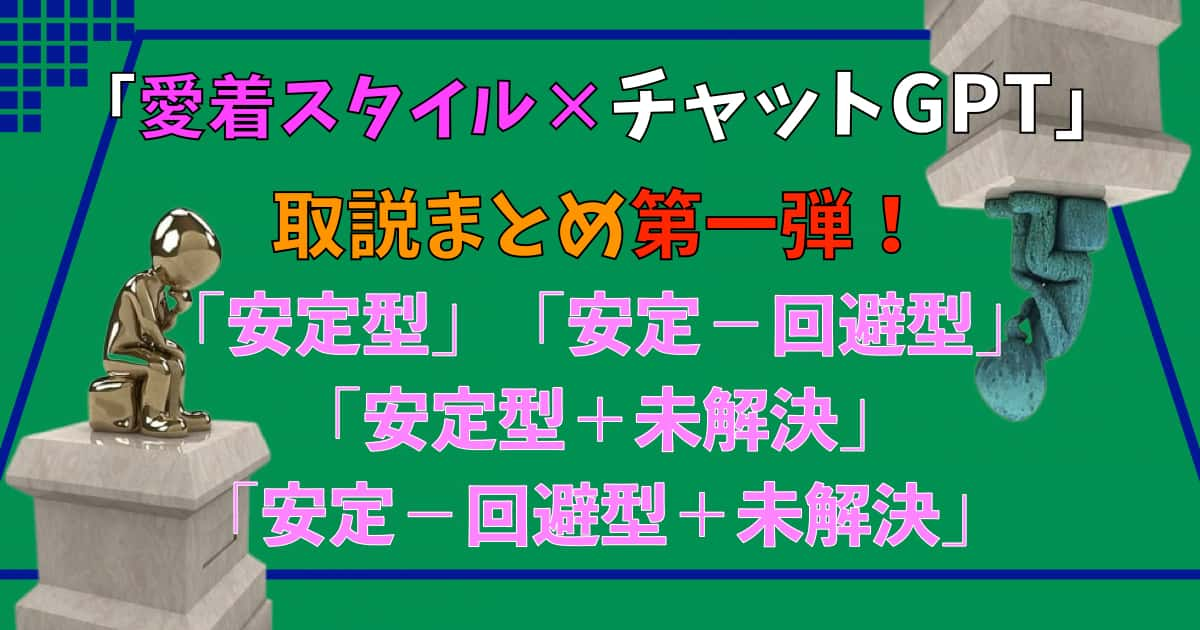
【安定型 愛着スタイル】取扱説明書
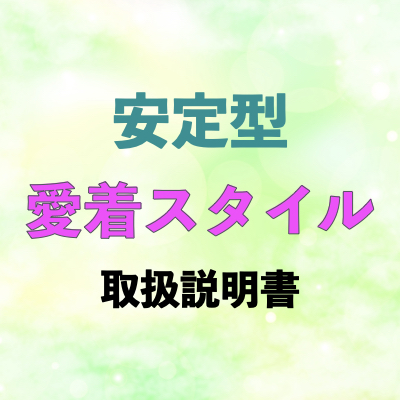
「人と心地よくつながれる力」を持つあなたへ──強みとケアのガイド
🔍 基本スペック(このタイプの主な特徴)
⚠️ 気をつけたいポイント
このスタイルは理想的ではあるけれど、「ずっと安定でいられる」わけではありません。
以下のような時に、自分でも気づかないストレスがたまることも。
・周囲の人(特にパートナーや家族)が不安型・回避型だと、自分が「支え役」になりすぎて疲れてしまう
・「私は大丈夫」と思って無意識に感情を抑えると、後から心や身体に影響が出ることも
・人間関係がスムーズなぶん、自分の本音や深層感情に目を向ける機会が減ることがある
🧭 取扱いのコツ(自分とのやさしい付き合い方)
🧰 オススメのツール&方法
🧘♀️ やさしさ瞑想(慈悲の瞑想)
→ 自分や他人へのあたたかい気持ちを育てる時間に
🧘♀️「やさしさ瞑想(慈悲の瞑想/メッタ・バーヴァナー)」は、仏教の瞑想法の一つで、自分や他人に向けて「思いやり」や「あたたかさ」を育てる練習です。
怒り・自己否定・不安・孤独などで心がざわつくときに、とても効果があります。
毎日5〜10分からでもOKです。
🧘♀️ やさしさ瞑想のやり方
① 静かな場所で、リラックスして座る
- 椅子でも床でもOK。背筋をやさしく伸ばし、目は閉じるか軽く伏せます。
- 数回、深呼吸して落ち着きます。
② 自分に向けて言葉を送る
心の中で、こんなフレーズをゆっくり繰り返します
🕊
「私が幸せでありますように」
「私が安全でありますように」
「私が健康でありますように」
「私の心が穏やかでありますように」
- 最初は感情がこもらなくても大丈夫。
- 「ただ言葉を繰り返すだけ」でOKです。
③ 身近な人を思い浮かべ、その人にも同じ言葉を送る
例:家族、友人、大切な人など
「○○が幸せでありますように」
「○○が安全でありますように」
「○○が健康でありますように」
「○○の心が穏やかでありますように」
- 感謝やあたたかい気持ちを込めると、さらに効果的です。
④ 徐々に範囲を広げていく
次のように広げていきます
- 自分
- 大切な人
- 中立な人(すれ違う人、店員さんなど)
- 苦手な人(ゆっくりでOK)
- すべての存在(生きとし生けるもの)
「すべての存在が幸せでありますように…」
⑤ 瞑想を終えるとき
- ゆっくり目を開け、数回深呼吸してから、今の心の状態を感じてみてください。
- 心が少しあたたかく、やわらかくなっていれば成功です。
💡 ポイント
- 感情が湧かなくてもOK。「ただ唱える」だけでも脳にポジティブな影響があります。
- 「苦手な人」に向けては無理にやらなくていいです。自分が嫌な気持ちにならない範囲で。
- 朝起きたとき、寝る前、電車の中などに短くやっても効果があります。
📓 気持ち日記・3行ジャーナル
→ 日々の感情や気づきをシンプルに書くだけでも、自己理解が深まります
1日を振り返って、「今の自分」にやさしく目を向けるためのミニ習慣。
書く内容は決まっていて、以下の3つの問いに答えるだけです。
📓 書き方(3つの質問)
① 今日あったこと(できごと)
例:「同僚にありがとうって言われた」「駅で転びそうになった」
② そのときの気持ち(感情)
例:「ちょっと嬉しかった」「恥ずかしかった」「疲れた」
③ 今、感じていること or 気づき
例:「ちゃんと人の役に立ててるかも」「人目を気にしすぎてるかも」
🖋 書くときのポイント
- 文章じゃなくても、単語だけ・箇条書きでもOK
- 「ポジティブなことを書かなきゃ」と思わなくていい
- つらかったこともOK。ジャッジしないでそのまま書くのが大切
- 手帳でもスマホでもOK(毎日続けやすい方法で)
🌱 続けるとどうなるの?
- 感情に気づきやすくなる
- どんな時に心が揺れるか、自分のパターンが見えてくる
- 無意識に「がんばりすぎていたこと」に気づく
- 自分への思いやりが育ってくる
- 感情を抑え込むクセが和らぎ、心の疲れがたまりにくくなる
🗓 書くタイミングは?
おすすめは 夜寝る前の3分間。
朝でも昼でもOKですが、1日の終わりに心を整える時間として取り入れると、睡眠の質も上がると言われています。
📍例:ある日の3行ジャーナル
① 今日は久しぶりに友達と電話した
② 安心したし、ちょっと泣きそうになった
③ 私って、本当は人とつながりたかったんだなって思った
📚 おすすめの本
クリスティン・ネフ (著), 石村 郁夫 (翻訳), 樫村 正美 (翻訳), 岸本 早苗 (翻訳), 浅田 仁子 (翻訳)
セルフ・コンパッション(自分への思いやり)の実証研究の第一人者であるクリスティン・ネフが、自身の体験と科学的知見を基に、セルフ・コンパッションの概念と実践方法をわかりやすく解説した一冊です。
この新訳版は、ストレスフルな現代社会で「疲れた自分」を癒し、自己受容を促すためのガイドとして再編集されました。
随所にエクササイズが含まれており、読みながら実践することで自然とセルフ・コンパッションを身につけられる構成になっています。
安定型愛着スタイルを持つ方にとって、自己の感情に気づき、他人に合わせすぎないバランスを保つためのツールとして特に役立ちます。
🧑🤝🧑 心理的に安全な人間関係を大切に
→ 安定型の人は「刺激より安心」が自分らしさを保つカギになります
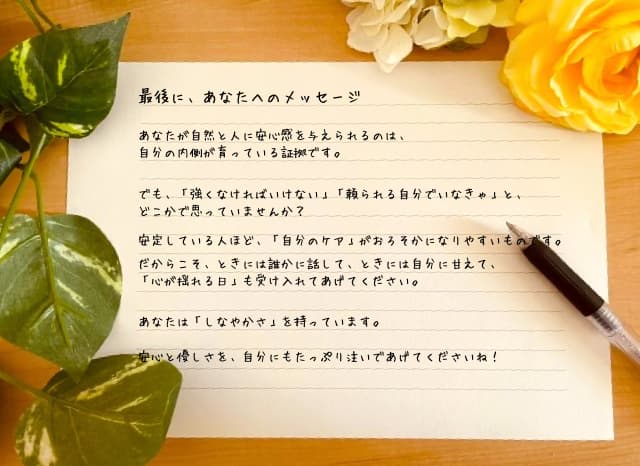
【安定-回避型 愛着スタイル】取扱説明書
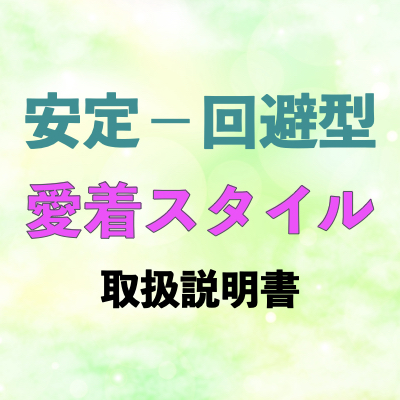
「つながりたいけど、自立も手放したくない」あなたのための、やさしいガイド
🔍 基本スペック(このタイプの主な特徴)
⚠️ よくある「つまずきポイント」
・人と深く関わるほど、「自由がなくなる」ように感じてしまう
・誰かに心配されたり、干渉されると「うっとおしい」と思ってしまう
・甘えたい気持ちがあっても、言葉にできない、「弱さを見せたくない」気持ちが強い
・相手に頼られると、「期待に応えなきゃ」とプレッシャーを感じて距離をとる
・一人の時間がないと、心が疲れる、でも孤独は嫌
🧭 取扱いのコツ(自分とのやさしい付き合い方)
🧰 オススメのツール&方法
🧘 ボディスキャン瞑想
→ 身体感覚を通じて、抑えてきた感情にやさしく気づける
- 頭のてっぺんから足の先まで、体の各部位に意識を向けて観察していく瞑想法。
- 「感じようとする」のではなく、ただ「気づく・あるがままを見守る」ことが目的。
- 不安・緊張・ストレスなどを、身体の感覚からやさしくほどいていく時間です。
⏳ 所要時間の目安
- 初心者は 5〜10分からでもOK。
- 慣れてきたら 20〜30分ほど取れると、より深いリラックスが得られます。
🪷 やり方(ガイド付き)
1. 静かな場所で、楽な姿勢に
- 仰向けに寝ても、椅子に座ってもOK。
- 目を閉じて、数回ゆっくり深呼吸しましょう。
2. 体の部位に順番に意識を向ける
順番は上から下、または下から上でもOKです。以下は下から始める例
👣 足先
「足の指先に、どんな感覚があるだろう?」「じんわりあたたかい?冷たい?しびれ?何も感じない?」
👉 判断せず、ただ観察します。
🦵 ふくらはぎ・膝・太もも
「重さ、緊張、だるさ、チクチク感などあるかな?」
👉 不快な感覚も、排除せずに「そうなんだな」と見守ります。
🫀 お腹・胸
→ 呼吸の動きや、心臓の鼓動に意識を向けると落ち着いてきます。
→「お腹のあたりに不安が溜まっている感じがする…」など、気づきが生まれることも。
🙌 手・腕・肩
→ 力が入っているところは、息を吐きながらやさしくゆるめます。
🧠 首・顔・頭
→ 顎・目元・額など、知らずに力が入っている場所に気づくことも。
3. 全身に意識を広げる
最後に、全身をひとつのまとまりとして感じてみましょう。
「いま、ここにいる自分」全体にやさしく注意を向けるだけでOK。
💡 コツと補足
- 「感じなきゃ」と力まずに、“何も感じない”こともそのまま受け取ってOK
- 急に感情がこみ上げてくることもあります。それは抑えていた気持ちが出てきているサイン
- 途中で眠くなっても大丈夫。身体がリラックスしようとしている証拠です。
🌱 どんな効果があるの?
- 感情やストレスが体にどう影響しているか気づけるようになる
- 緊張・不安・怒りなどをためこみにくくなる
- 頭ばかり使いすぎていた状態から、身体を通じて“今ここ”に戻ってこられる
📓 モーニングページ(日記習慣)
→ 毎朝3ページ、頭の中にあることをそのまま書き出すことで「心の解凍」が起こります
- アーティストや作家のための自己開放ワークとして、ジュリア・キャメロンの著書
『The Artist’s Way(邦題:ずっとやりたかったことを、やりなさい。)で紹介された方法。 - 毎朝起きてすぐ、頭に浮かんでいることを3ページ分ノートに書くというシンプルなもの。
✍️ やり方(ステップガイド)
1. 朝、起きたらすぐ書く
- なるべくスマホを見る前に。
- 頭がスッキリしていなくてもOK。むしろ「もやもや」してるからこそ意味があります。
2. ノートに3ページ、手書きで書く
- A4サイズのノートで3ページ(だいたい15〜20分程度)。
- 内容はなんでもOK
- 「眠い」「めんどくさい」「今日の予定なにしよう」
- 「昨日のあの言葉が引っかかってる」
- 「コーヒー飲みたいな」……など、まとまっていなくてOK。
3. 止まらずに、とにかく書く
- 誤字も文法も気にしなくて大丈夫。
- 書くことがなくなったら、「書くことがない」と書いてもOK。
4. 誰にも見せない前提で書く
- 書いたものは読み返さなくてもいいです(読み返すのは8週間後でもOK)。
- とにかく「吐き出す」ことが目的。
💡 モーニングページの効果
- ☁️ 頭の中のもやもやを「見える化」して、スッキリする
- 🧠 無意識の思考・感情にアクセスできる(=心の奥とつながる)
- 🎨 創造性が回復する
- 🧘♀️ 感情のリセット・セルフセラピー効果がある
✅ 続けるコツ
- 書く前に「正解を探さない」「きれいに書こうとしない」と自分に言い聞かせる
- 朝が難しい日は「午前中」でもOK。とにかく「その日の自分を一度、紙に出す」ことが大切です
- 3ページがキツい日は、1ページからでも◎。継続が何よりの力になります
📎 書き出しの例(参考)
- 「今日はなんとなく憂うつ。理由ははっきりしないけど、昨日のあの会話のせいかも」
- 「頭が重い。ちゃんと寝たはずなのに…生理前かな」
- 「これってただの愚痴? でも書いてたら少し楽になってきた」
📖 おすすめの本
藤野智哉 (著)
人間関係で「なんとなく疲れてしまう」「距離の取り方がわからない」「断るのが苦手」……そんなあなたに向けて、精神科医の著者が提案するのは「バウンダリー(心の境界線)」という考え方。
この本は、「嫌われたくない」「迷惑をかけたくない」と無意識に他人を優先してしまう人が、自分を守りながら、健やかな人間関係を築くための“心の距離感”を学ぶ実践的な一冊です。
【読後の効果】
- 「線を引く」ことは冷たさではなく、自分と他人を大切にすることだと実感できる
- 罪悪感なく断る力、距離をとる力が育まれる
- 無理せず人と関わる方法がわかるようになる
⬇️⬇️⬇️実際の商品ページに飛びます⬇️⬇️⬇️
👥 安心できる少人数の関係性を育てる
→ 無理に多くの人と深くつながらなくて大丈夫。1人か2人、気楽にいられる相手がいれば十分です
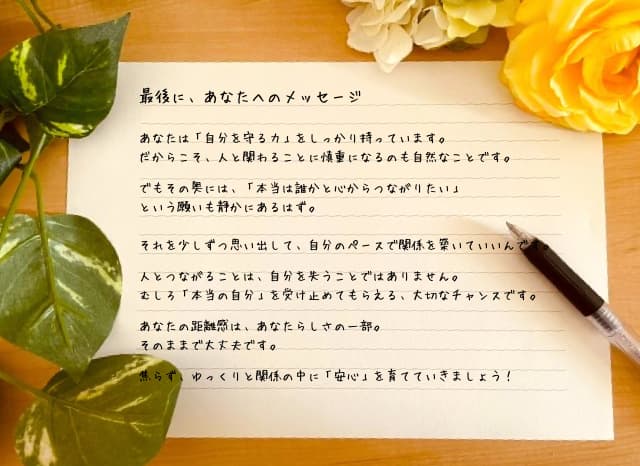
【安定型+未解決 愛着スタイル】取扱説明書
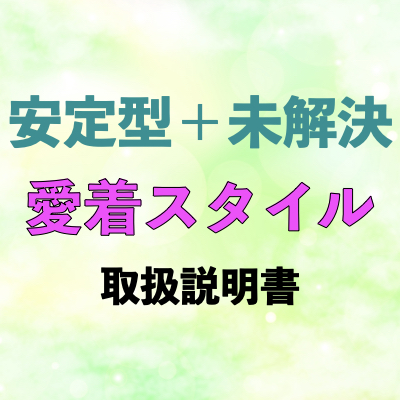
「ふだんは安定。でも、ふとしたときに揺らぎやすい」あなたのための、こころのガイドブック
🔍 基本スペック(このタイプの主な特徴)
⚠️ よくある「つまずきポイント」
・日常では安定しているのに、特定の人・シチュエーションで強く感情が動く
・急に自己否定が強まったり、不安や孤独感に襲われたりする
・「大したことないはずなのに涙が出る」「うまく言葉にできない」感覚がある
・「ちゃんとしてるのに、なぜか生きづらい」と感じることがある
・自分でも理由がわからないまま、落ち込んでしまうときがある
🧭 取扱いのコツ(自分とのやさしい付き合い方)
🧰 オススメのツール&方法
🧘 マインドフルネス瞑想
→ 揺れた心を「今ここ」に戻す習慣づけに。呼吸に意識を向けるだけでも効果あり
✨目的
- 「今ここ」に意識を戻すことで
- 思考や感情に飲み込まれず、穏やかな気づきを持てるようにする
🪷 1日3〜10分のマインドフルネス瞑想【基本のやり方】
① 姿勢をととのえる
- 椅子に腰かけるか、床に座ります(あぐら・正座でもOK)
- 背筋をやさしく伸ばし、肩の力を抜きます
- 目は軽く閉じるか、半眼で一点をぼんやり見つめる
② 呼吸に意識を向ける
- 「息を吸っている」「息を吐いている」と気づくだけ
- 呼吸をコントロールしなくていい。自然な呼吸を感じます
- 空気が鼻を通り、胸やお腹がふくらんだり縮んだりする感覚に注意を向けます
③ 雑念が浮かんだら…
- 思考(予定、不安、考え事など)が出てきたら、
「あ、今考えてるな」と気づいて、やさしく呼吸に戻る - 自分を責めずに、「戻ること」が瞑想の一部です
④ 終わるとき
- 1分ほど静かにして、全身の感覚を感じてみる
- ゆっくり目を開け、日常に戻ります
🎧 こんなフレーズを心で唱えてもOK
「吸っている、吐いている」
「今、ここにいる」
「私は落ち着いている」
「ただ呼吸しているだけ」
⏰ 取り入れやすいタイミング
- 朝の始まりに(1日の土台が整います)
- 昼休み、作業の切れ目に(リセットになります)
- 寝る前の3〜5分(不安やモヤモヤを落ち着かせる)
🌿 続けるとどうなる?
- 思考の「暴走」に気づけるようになる
- 不安やイライラが長引きにくくなる
- 集中力・自己理解が高まる
- 心がやわらかく、穏やかになる
- どんな感情も「そのまま味わえる」力が育つ
💬 よくある勘違い
- 「雑念が出てきたらダメ」→ ❌大丈夫です。気づけた時点で成功です。
- 「無にならなきゃいけない」→ ❌必要ありません。気づいて戻る、それだけでOK
📓 エモーショナル・ジャーナリング(日記)
→ 感情のトリガーや心の動きを言語化することで、客観視しやすくなります
- 感情の揺れやもやもやを、思考ではなく「言葉」で出していくワーク
- 書くことで、自分の気持ちを客観視・整理・受容できるようになる
- 続けるほど、自己理解・感情調整力・回復力(レジリエンス)が育つ
🖋 基本の書き方(ステップ)
① 感情が動いた場面を思い出す/起こったことを書く
✔︎ 今日腹が立ったこと、悲しかったこと、引っかかったこと
✔︎ 具体的な出来事・言葉・状況などをなるべく思い出して
例:「朝、上司にあいさつしたけど無視された。なんだかすごくモヤモヤした」
② そのときの感情を言葉にする
✔︎ 「怒り」「さみしさ」「不安」「情けなさ」「虚しさ」など、感情に名前をつける
✔︎ いくつでもOK。言葉にならなければ「よくわからない感情」でもOK
例:「無視されたことで、寂しさ・怒り・否定されたような気持ちがあった」
③ なぜその感情が湧いたのか、自分の内側に問いかけてみる
✔︎ 自動思考・思い込み・昔の記憶とのつながりなど
✔︎ 「本当はどう感じた?」「何を怖がってた?」と聞いてみる
例:「“ちゃんと見てほしい”って思ってたのかもしれない」
例:「過去に父親に無視された記憶と重なったのかも」
④ 書きながら出てきた気づき・学び・癒しをまとめる
✔︎ 「なるほど、私は〜と思ってたんだな」など
✔︎ 優しい言葉で、自分をフォローして締めると効果的
例:「私、もっと認められたかったんだな」
例:「それに気づけたのは大きい。ちゃんと自分に寄り添ってあげたい」
🪞 よく使われる問いのテンプレート(気づきやすくなる質問)
- 何があったの?
- どんな気持ちが湧いた?
- その気持ちを、体のどこで感じた?
- なぜそれがつらかったの?
- 本当は何を望んでいたの?
- この出来事は、自分に何を教えてくれた?
- 今、何をしてあげたら落ち着けそう?
🕰 おすすめの頻度と時間
- 1回15〜30分ほど。週1でもOK、感情が揺れたときだけでもOK
- 夜寝る前や、週末など「少しだけ自分に戻れる時間」に
📖 おすすめの本
べッセル・ヴァン・デア・コーク (著), 柴田 裕之 (翻訳)
未解決型の「説明のつかない不安や空虚感」に深く関係するトラウマの影響を、身体と心のつながりから解説。「近づく=危険」の癖を緩和し、安心感を育む方法を学べます。
トラウマが脳や身体にどう影響するか、科学的データと事例で説明。ヨガやマインドフルネスなど、身体を通じて安心感を再構築する実践法を提案。
この本は、精神科医であり、トラウマ研究の世界的第一人者である著者が、「心の傷(トラウマ)」がいかにして脳・神経・身体に影響を与え、人生を無意識のうちに支配してしまうかを解き明かし、そこからの回復の道筋を提示した一冊です。
トラウマは、単に「つらい記憶」ではありません。
過去の経験が思考や感情だけでなく、身体反応や神経系そのものにまで染みついているのです。
「些細なことでフラッシュバックする」「大人になっても理由のわからない不安や緊張が続く」といった現象は、身体が“記憶している”トラウマの反応であり、意志や論理では消せません。
「話すこと」だけでは、癒せない。
体に刻まれた記憶にこそ、真の回復の鍵がある。
この本はやや専門的な部分もありますが、実際の臨床ケースが豊富で、物語のように読める箇所も多いため、一般読者にも十分理解できる構成になっています。
読みごたえはありますが、「生きづらさの正体」に深く迫りたい方には必読の一冊です。
⬇️⬇️⬇️実際の商品ページに飛びます⬇️⬇️⬇️
👥 カウンセリング・トラウマ療法(EMDR、スキーマ療法など)
→ 心の深い層を扱うサポートがあると、安心して解きほぐしていけます
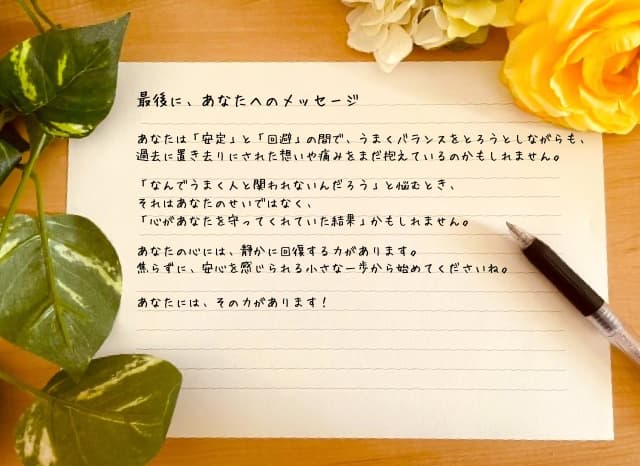
【安定-回避型 + 未解決型 愛着スタイル】取扱説明書
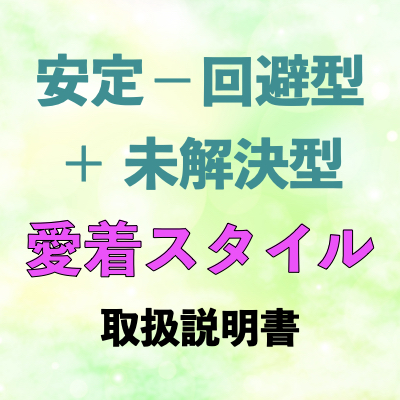
あなたのこころのクセと、じっくり向き合うためのガイド
🔍 基本スペック(このタイプの主な特徴)
⚠️ よくある「つまずきポイント」
・深く仲良くなれそうな人と話していると、どこかで「引きたくなる」感覚がある
・「頼る」「甘える」が苦手で、弱さを見せることに強い抵抗がある
・相手からの好意を受け取ると、無意識に距離をとる
・日常では安定しているのに、ふとした瞬間に感情の波が襲ってくる
・自分の感情を言語化しようとすると、うまく言えなかったり混乱したりする
🧭 取扱いのコツ(自分とのやさしい付き合い方)
🧰 オススメのツール&方法
🧘 マインドフルネス
→ 今ここに意識を戻すことで、不安を鎮めるトレーニングに
✨目的
- 「今ここ」に意識を戻すことで
- 思考や感情に飲み込まれず、穏やかな気づきを持てるようにする
🪷 1日3〜10分のマインドフルネス瞑想【基本のやり方】
① 姿勢をととのえる
- 椅子に腰かけるか、床に座ります(あぐら・正座でもOK)
- 背筋をやさしく伸ばし、肩の力を抜きます
- 目は軽く閉じるか、半眼で一点をぼんやり見つめる
② 呼吸に意識を向ける
- 「息を吸っている」「息を吐いている」と気づくだけ
- 呼吸をコントロールしなくていい。自然な呼吸を感じます
- 空気が鼻を通り、胸やお腹がふくらんだり縮んだりする感覚に注意を向けます
③ 雑念が浮かんだら…
- 思考(予定、不安、考え事など)が出てきたら、
「あ、今考えてるな」と気づいて、やさしく呼吸に戻る - 自分を責めずに、「戻ること」が瞑想の一部です
④ 終わるとき
- 1分ほど静かにして、全身の感覚を感じてみる
- ゆっくり目を開け、日常に戻ります
🎧 こんなフレーズを心で唱えてもOK
「吸っている、吐いている」
「今、ここにいる」
「私は落ち着いている」
「ただ呼吸しているだけ」
⏰ 取り入れやすいタイミング
- 朝の始まりに(1日の土台が整います)
- 昼休み、作業の切れ目に(リセットになります)
- 寝る前の3〜5分(不安やモヤモヤを落ち着かせる)
🌿 続けるとどうなる?
- 思考の「暴走」に気づけるようになる
- 不安やイライラが長引きにくくなる
- 集中力・自己理解が高まる
- 心がやわらかく、穏やかになる
- どんな感情も「そのまま味わえる」力が育つ
💬 よくある勘違い
- 「雑念が出てきたらダメ」→ ❌大丈夫です。気づけた時点で成功です。
- 「無にならなきゃいけない」→ ❌必要ありません。気づいて戻る、それだけでOK
📓 感情トラッキング(日記)
→ 日々の「心の揺れ」を言語化することで、自分の心の流れを可視化できます
- 1日の中で感じた感情・心の揺れを「意識的に書き出す」ことで、モヤモヤや不安の正体が少しずつ見えてくるようになります。
- 感情を言葉にして見える形にすることが、心を落ち着ける手助けになります。
✍️ 書き方の基本(5分あればOK)
① 今日あったできごと(トリガー)
例:「上司に話しかけられた」「友達から既読無視された」
② その時に感じた感情(できるだけ具体的に)
例:「緊張」「不安」「イラッとした」「さみしかった」「うれしかった」
③ 感情の強さ(0〜10で数値化)
例:「不安=7」「怒り=3」など
→ 数値化することで「意外と強く感じてたな」と客観視できます
④ その後どう反応した?(思考・行動)
例:「無理に笑ってごまかした」「何も言えず黙ってしまった」
⑤ 今ふり返って感じること・気づき
例:「本当はもっと気楽に話したかった」「傷つくのが怖くて遠ざけたかも」
🧠 続けることで見えてくること
- どんな状況や人に反応しやすいか(自分のトリガー)
- どんな感情パターンがよく出てくるか(不安・怒り・罪悪感など)
- 感情と行動のつながりやクセ(我慢・回避・過剰反応など)
📘 感情ラベルが思いつかないときは?
以下のような「感情一覧表」を参考にしてもOKです
- 不安・緊張・さみしさ・怒り・恥ずかしさ・罪悪感・安心・感謝・喜び・退屈・疲労感
👉 特にネガティブ感情は書きづらいですが、抑えるより、書くことで軽くなります。
🗓 書く頻度と続け方のコツ
- 週に数回でも、1日1つの出来事でも十分です
- 書いたあと、「あ〜そう感じてたんだな」とジャッジせず読み返すことが大切
- 手書きでもスマホでもOK(人に見せなくていいので正直に)
📖 おすすめの本
クリスティン・ネフ (著), 石村 郁夫 (翻訳), 樫村 正美 (翻訳), 岸本 早苗 (翻訳), 浅田 仁子 (翻訳)
「感情が出てこない」状態や自己批判を緩和し、「感じたままを許す」姿勢を養うのに有効。回避型の方が弱さを見せる抵抗を減らし、自己受容を促す具体的なエクササイズが豊富。
セルフ・コンパッションの3要素(自己への優しさ、共通の人間性、マインドフルネス)を解説。感情の波や空虚感に直面した時の対処法を、科学的根拠と実践で提供。
セルフ・コンパッションの実証研究の第一人者であるクリスティン・ネフが、自身の体験と科学的知見を基に、セルフ・コンパッションの概念と実践方法をわかりやすく解説した一冊です。
この新訳版は、ストレスフルな現代社会で「疲れた自分」を癒し、自己受容を促すためのガイドとして再編集されました。
随所にエクササイズが含まれており、読みながら実践することで自然とセルフ・コンパッションを身につけられる構成になっています。
安定型愛着スタイルを持つ方にとって、自己の感情に気づき、他人に合わせすぎないバランスを保つためのツールとして特に役立ちます。
べッセル・ヴァン・デア・コーク (著), 柴田 裕之 (翻訳)
未解決型の「説明のつかない不安や空虚感」に深く関係するトラウマの影響を、身体と心のつながりから解説。「近づく=危険」の癖を緩和し、安心感を育む方法を学べます。
トラウマが脳や身体にどう影響するか、科学的データと事例で説明。ヨガやマインドフルネスなど、身体を通じて安心感を再構築する実践法を提案。
この本は、精神科医であり、トラウマ研究の世界的第一人者である著者が、「心の傷(トラウマ)」がいかにして脳・神経・身体に影響を与え、人生を無意識のうちに支配してしまうかを解き明かし、そこからの回復の道筋を提示した一冊です。
トラウマは、単に「つらい記憶」ではありません。
過去の経験が思考や感情だけでなく、身体反応や神経系そのものにまで染みついているのです。
「些細なことでフラッシュバックする」「大人になっても理由のわからない不安や緊張が続く」といった現象は、身体が“記憶している”トラウマの反応であり、意志や論理では消せません。
「話すこと」だけでは、癒せない。
体に刻まれた記憶にこそ、真の回復の鍵がある。
この本はやや専門的な部分もありますが、実際の臨床ケースが豊富で、物語のように読める箇所も多いため、一般読者にも十分理解できる構成になっています。
読みごたえはありますが、「生きづらさの正体」に深く迫りたい方には必読の一冊です。
⬇️⬇️⬇️実際の商品ページに飛びます⬇️⬇️⬇️
👥 安心できる対話環境(カウンセリング・傾聴)
→ 無理に変えなくても、聴いてもらうだけで「自己の感情に気づく」練習に
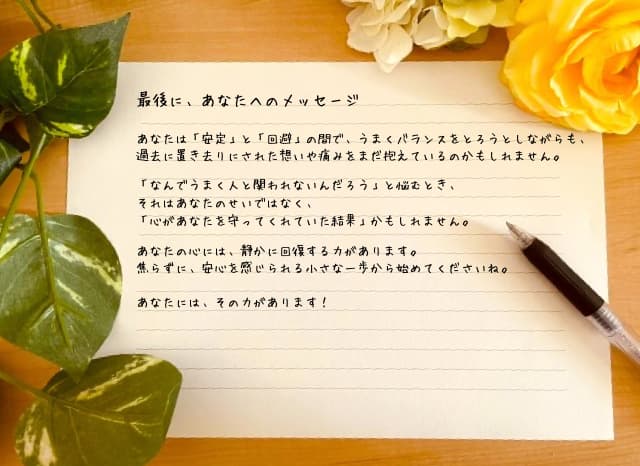
まとめ
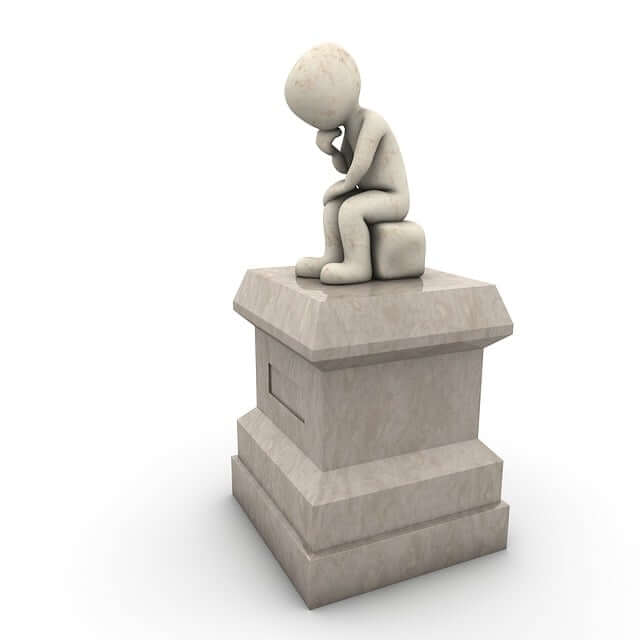
今回は、「安定型」「安定-回避型」「安定型+未解決」「安定-回避型+未解決」の取説まとめを紹介してきました!
- 「安定型」だとしても、「ずっと安定でいられる」わけではなく、自分でも気づかないストレスが溜まることもある。
- 「安定-回避型 」が人との距離をうまく保とうとすることは、「冷たい」のではなく、自分を守るための自然な感覚。
- 「安定型+未解決」の日常的には落ち着いていても、時々訪れる心の揺れは「未解決の記憶」が呼び起こされているから。
自分の中に潜む、言葉にしづらい、人にわかってもらえないもの・・・
人生って生きづらいなと思って過ごしておられる方も、たくさんいると思います。
そんな方の助けに、少しでもなれたらいいなと思いました☺️
次回、「愛着スタイル×チャットGPT」取説まとめ第二弾!「不安型」「不安-安定型」「不安型+未解決」「不安-安定型+未解決」へ続きます!
最後までお読みいただきありがとうございました!


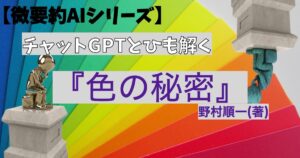


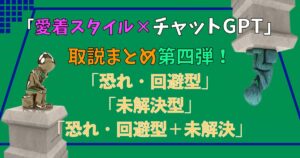
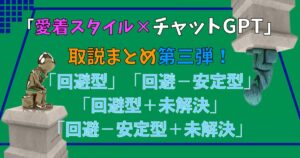
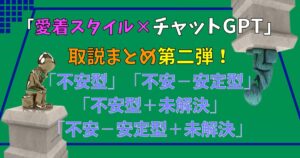

コメント