この記事は、『感情を引き出す小説の技巧 読者と登場人物を結びつける執筆術』ドナルド・マース (著)/佐藤弥生訳/茂木靖枝訳(フィルムアート社, 2022年)の第1章をチャットGPTとひも解く内容となっています。

読者の感情を引き出す・・・って、これ相当難しいことな気がする・・・

主人公の心情とか語れば、読者も勝手に感情的になるんじゃね?

確かに主人公の置かれてる状況は伝わるけど、それで読者の感情を引き出せてると言えるのか・・・?
- 「見せること」と「語ること」は、読者の感情にほとんど影響しない
- 「見せること」と「語ること」が読者の感情にはほとんど影響を及ぼさないについてチャットGPTに聞いてみた!
- 小説を書くとき感情というレンズを通すことが重要な理由
はじめに・・・
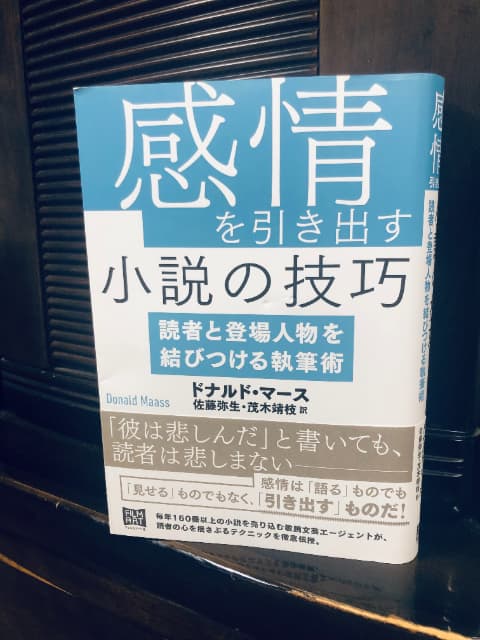
『感情を引き出す小説の技巧 読者と登場人物を結びつける執筆術』とは、毎年150冊以上の小説を売り込む文学エージェント、ドナルド・マース氏による著書です。
※文学エージェント:著者に代わって出版社に原稿を売り込む人
感情は「見せるもの」か、それとも「語るもの」か───。
一般的に言われてきた感情表現のパターンですが、本書は「見せること」も「語ること」も、読者の感情を動かす要因にはほとんどならないとしています。
感情は「見せる」ものでも、「語る」ものでもなく「引き出す」ものなのです!
読者は小説をよむというよりもむしろ「反応」しており、強烈で印象深い感情を引き出す「体験」を目指すべきなのです。
本書では、数多くの小説作品を引用しながら感情面への衝動の仕組みを実感し、「体験」をもたらすための効果的な技術や、語りかた、その他多くの技術を解説しています。
「見せること」と「語ること」は、読者の感情にほとんど影響しない
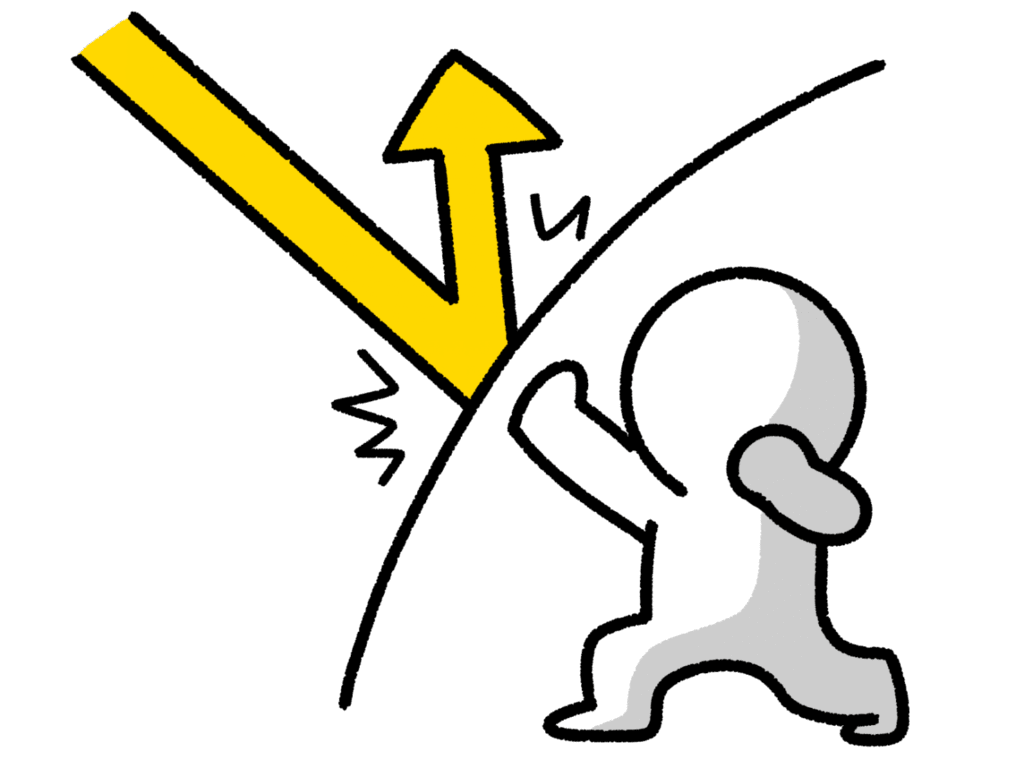
結論から述べると、「見せること」と「語ること」は、読者の感情にほとんど影響せず、最も重要なのは「どうすれば読者自身の感情を動かすことができるか」です。
まずはじめに、マース氏いわく、「見せること」を重視している感情を文章にするのを嫌う作家と、「語ること」を重視している感情を書くのを好む作家に分けられるそうです。
つまり、「見せること」を重視している作家は、登場人物の気持ちや考えを読者も感じられるように、登場人物の経験を書いてゆき、その「瞬間」を捉えて、読者の感情を引き出していきます。
このタイプの作家は、細部に凝って説明せずに、ありのままの描写で言葉を超えた表現を好み、よって感情を文章にするのを嫌うというわけです。
反対に「語ること」を重視している作家は、登場人物の心にシンクロし、その人物と同じ目線で観察します。
こうした作家は、言葉の力のみで登場人物の内面を細部まで逃さず表現することを重要視しており、よって感情を書くのを好むというわけですね。
小説を読んでいると、だいたいこの2つのタイプのどちらかの文章だったりします(わたしは、前者の方が好きかな……)。
ただ、どんな作家もどちらかの技法のみを使っているわけではなく、その二つをうまく利用して書いています。
「見せること」と「語ること」が読者の感情にはほとんど影響を及ぼさないについてチャットGPTに聞いてみた!
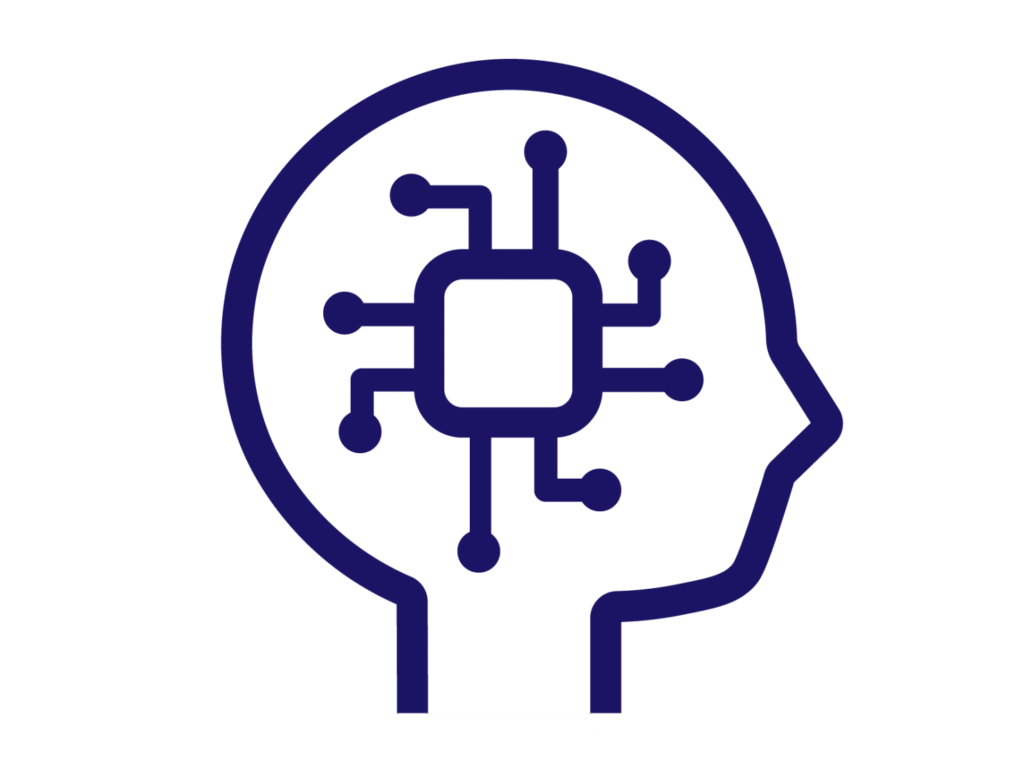
しかし、著書いわく、
「見せること」と「語ること」は、技法としてはよいのですが、読者の感情にはほとんど影響を及ぼしません。
と述べているのです。

『感情を引き出す小説の技巧 読者と登場人物を結びつける執筆術』ドナルド・マース (著)/佐藤弥生訳/茂木靖枝訳では、「見せること」と「語ること」は、技法としてはよいのですが、読者の感情にはほとんど影響を及ぼしません。と述べているのですが、どう思いますか?

この指摘はかなり本質的で、私も賛成です。
「見せること(Show)」と「語ること(Tell)」は確かに文章技法として重要ですが、それ自体はあくまで表現の“形”にすぎません。形だけでは、読者の感情を揺さぶる保証にはならないのです。
チャットGPTがもっともらしいことを言っていますね・・・
例えば、
「彼は拳を握りしめた(見せる)」
「彼は怒っていた(語る)」
このどちらも、状況や感情を理解させることはできますが、読者が本当に感情移入して胸が熱くなるとは限りません。
読者の感情を引き出すためには、形よりも感情の源泉にアクセスすることが必要です。
ドナルド・マースが言いたいのは、おそらくこういうことです。
- キャラクターの感情と読者の感情がリンクする瞬間を作る
- 単なる描写ではなく、読者自身の記憶や価値観に触れるような要素を入れる。
- コンフリクトや選択の重みを描く
- 登場人物が何かを失いそうになる、または得るために大きな代償を払う瞬間は、読者の心を動かしやすい。
- 感情の“裏”を描く
- 喜びの裏にある不安、怒りの裏にある悲しみなど、複雑な層を見せることで深く響く。
つまり、見せる/語るはあくまで「道具」であり、読者の感情に影響を与えるのはその道具を通して何を伝えるかなんです。
これは、料理でいうと包丁さばきが上手くても、素材や味付け次第で印象がまったく変わるのと同じですね。
※コンフリクトとは、物語の中でキャラクターが直面する対立や葛藤のことです。単にケンカや争いを指すだけではなく、もっと広い意味で、主人公の望みを邪魔する力すべてがコンフリクトになります。
チャットGPTの解釈では、「見せること」と「語ること」はあくまで「道具」で、読者の感情を引き出すためには、
などを通して、感情の源泉にアクセスすることが大事とのことです。
なかなか良い線いっているのではないでしょうか?
チャットGPTに本書の結論を伝えてみた
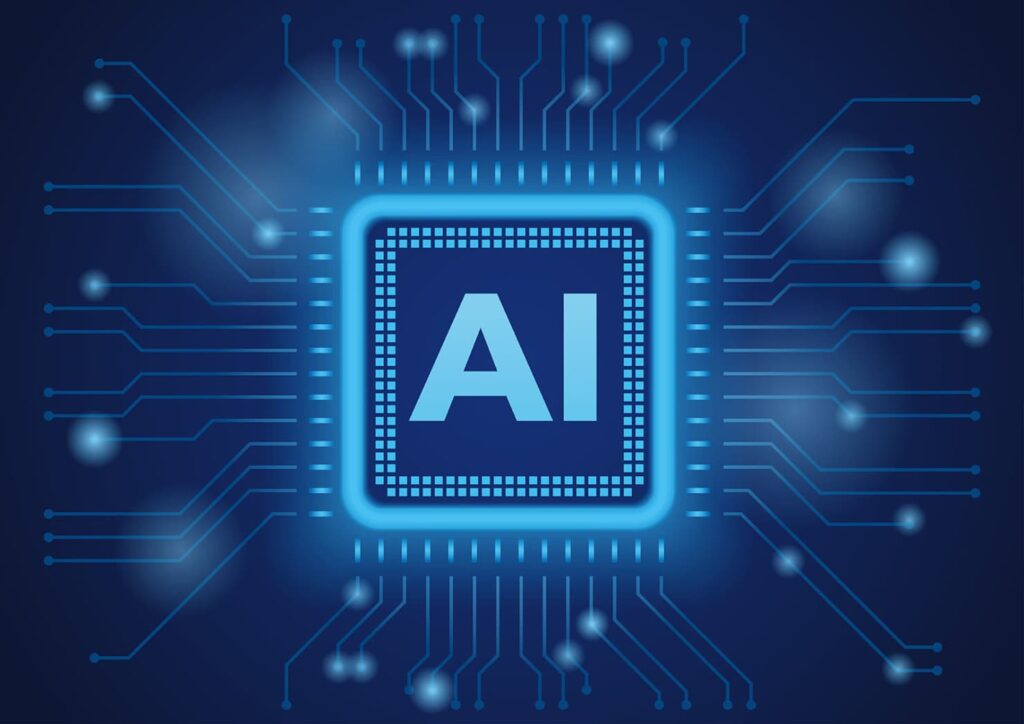
では、チャットGPTの答えも出たことですし、本書の答えを伝えてみようと思います。

「見せること」と「語ること」は、読者の感情にほとんど影響せず、最も重要なのは「どうすれば読者自身の感情を動かすことができるか」とマース氏自身も述べています。

そうですね、その通りです。
ドナルド・マース氏の立場は、いわばこういう整理になります。
「見せる(Show)」や「語る(Tell)」は手段にすぎない
→ 表現のスタイルや情報の出し方は、文章を分かりやすくしたり臨場感を持たせるには有効だが、それだけでは読者の心は深く動かない。
本当に重要なのは「読者の感情を動かす」こと
→ そのためには、読者が物語を通して自分自身の記憶や価値観と結びつくような瞬間を作らなければならない。
マース氏の方法論では、読者の感情を動かすための要素として、
・キャラクターが直面する内面的な葛藤
・失う恐れ・危機感・切迫感
・キャラクターの選択による代償
・感情の複雑さ(喜びと悲しみが混ざる等)
などが強調されるのではないでしょうか。
つまり、彼の主張は
「見せる/語る」は道具箱の中の一つの工具であって、作品の“心臓”は読者の感情を揺さぶる構造そのものである。ということですね。
包丁やフライパンだけでは料理が完成しないのと同じで、見せる/語るだけでは感動は生まれない、という感覚に近いです。
チャットGPTは作品の“心臓”は読者の感情を揺さぶる構造そのものとのことです。
要は主人公に困難をぶつけて、意図的に読者の感情を揺さぶる構造を作ることで、読者が自分自身の記憶や価値観と結びつくような瞬間が生まれるのでは?ということです。
ただ、これはあくまでチャットGPTの解釈です。
小説を書くとき感情というレンズを通すことが重要な理由
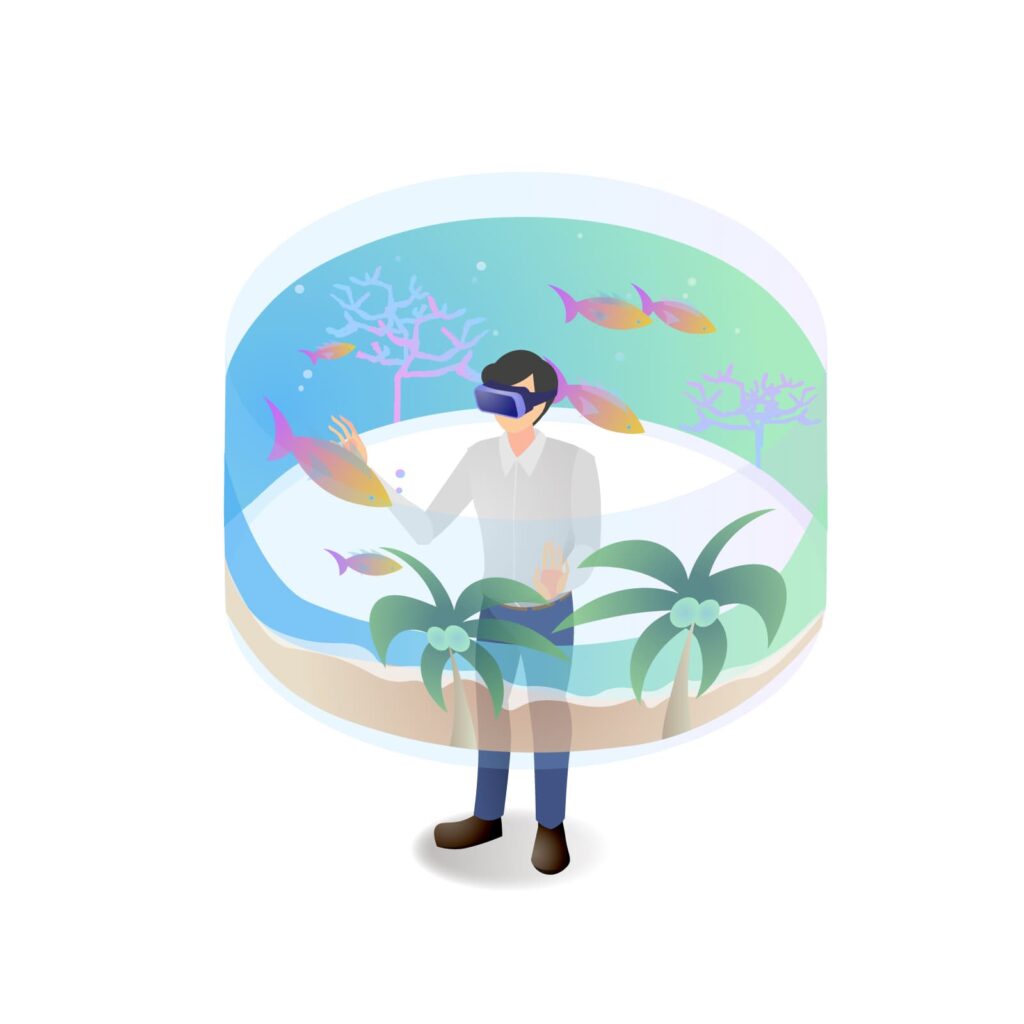
マース氏いわく、小説を書くときに感情というレンズを通すことが重要とのことですが、それはなぜなのでしょうか?
結論を言うと、「読者がそのように読んでいるから」です。
では、まずチャットGPTに予想を立ててもらいましょう。

マース氏いわく、小説を書くときに感情というレンズを通すことが重要とのことですが、なぜだと思いますか?

マース氏が「感情というレンズを通すこと」を重視するのは、読者が物語を知識として理解するのではなく、体験として感じるためです。
理由を整理するとこうなります。
1. 感情は記憶に残りやすいから
人間は、出来事そのものよりも、それによって生じた感情を長く覚えています。
物語を感情を通して描くと、読者は場面を「心で」記憶するので、読み終えた後も印象が強く残ります。
2. 感情が読者とキャラクターをつなぐから
感情をレンズにすれば、読者はキャラクターの行動や選択を頭で理解するだけでなく、同じ感覚を共有できます。例えば「父親を失った悲しみ」を描くとき、事実の説明だけではなく、その瞬間の感覚・身体反応・世界の見え方まで描くことで、読者も心の奥で共鳴します。
3. 感情は普遍的な“翻訳機”だから
文化や時代が違っても、恐れ・愛・希望・喪失感といった基本的な感情は誰にでも理解できます。
感情を通せば、読者は自分とは違う世界や立場のキャラクターにも共感でき、物語世界に入り込みやすくなります。
4. 行動や出来事に“意味”を与えるから
同じ出来事でも、感情の角度から描くと意味が変わります。
【例】
- 客観的描写 → 「雨が降っている」
- 感情のレンズ → 「雨が降るたびに、あの日の別れを思い出す」
これによって出来事が単なる背景ではなく、物語の一部として読者の心に作用します。
まとめると、マース氏の考えは
感情は物語を“事実の羅列”から“読者自身の体験”へ変える装置ということです。
チャットGPTは、読者が物語を知識として理解するのではなく、「体験」として感じるからとして、4つも根拠を挙げてくれました。
ただ、マース氏の答えの方が感情のままに読むという本質的な言葉だと感じました。

マース氏の答えは、「読者がそのように読んでいるから」です。

なるほど、マース氏の答えは非常にシンプルで本質的ですね。
つまり、感情というレンズを通すのは理論や技巧のためではなく、読者の読み方そのものに合わせるため、ということです。
読者は無意識のうちに、物語を感情のフィルターで読んでいる、キャラクターの行動や出来事を理解する際も、まず自分の感情に照らして受け取る。
だから、作者もその感情レンズを意識して書かないと、読者とのズレが生まれる。
言い換えると、文章の形式や描写の精巧さよりも、読者が自然に感情を通して体験できるかどうかが小説の命になる、ということです。
要はマース氏はこう言っているわけです。
「読者はすでに感情のレンズで読んでいる。作者も同じレンズを通して書くことで、初めて読者とつながる」
マース氏いわく、読者は読むと言うより反応しているそうです。
そして作家は、さまざまな考え方を持った読者の感情をただ引き出すということをしています。
読者を反応させながら、読者の感情をうまく引き出すことで、読者の心に「衝撃」を与えていくということですね。
マース氏はこう語っています。
例えば、伏線の回収、魅力的な書き出し、予想を裏切られる展開といったような効果は、その場面を過ぎると跡形もなく忘れてしまうのです。
10年、20年経っても忘れない作品は、うまく感情を引き出され、心に「衝撃」が刻まれているので、読んだときの感情がいつまでも心にあるのです。
まとめ

今回は、『感情を引き出す小説の技巧 読者と登場人物を結びつける執筆術』の内容の一部を、チャットGPTと一緒にひも解いていきました。
- 「見せること」と「語ること」は、読者の感情にほとんど影響せず、最も重要なのは「どうすれば読者自身の感情を動かすことができるか」。
- 「『見せること』と『語ること』は、技法としてはよいが、読者の感情にはほとんど影響を及ぼさない」ことに対するチャットGPTの答えは、「見せること」と「語ること」はあくまで「道具」で、読者の感情を引き出すため感情の源泉にアクセスすることが重要。
- 小説を書くときに感情というレンズを通すことが重要な理由。マース氏:「読者がそのように読んでいるから」。チャットGPT:「読者が物語を知識として理解するのではなく、体験として感じるから」。
わたし自身もシナリオライターの端くれですが、見せたり語ったりさせることは意識して物語を楽しんでもらうにはどうすればいいか常に考えています。
ただ、読者の感情を引き出して体験させるという視点は、わかっていたようで全然わかってなかったと再認識させられました。
今回はこれで以上です!最後までお読みいただきありがとうございました!





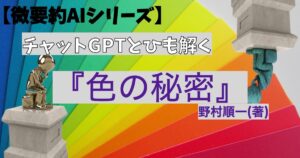

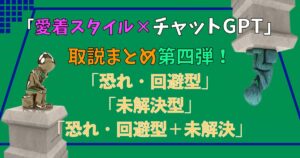
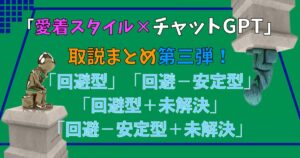
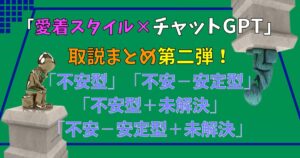
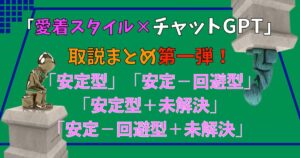

コメント