この記事は、『キャラクターからつくる物語創作再入門』K.M.ワイランド(著)/シカ・マッケンジー(訳)(フィルムアート社, 2019/3/25)をチャットGPTとひも解く内容となっています。

キャラクターからつくる物語って聞くとどう思う?

キャラが際立つまで、キャラの性格とか特徴を深掘りしたあとに、物語に登場させてどうこうみたいな?

魅力的なキャラを生み出してってことなんだけど、その一つにキャラが信じ込んでいる「嘘」を設定するというものがあるんです。
- キャラクターが信じ込んでいる嘘とは?
- 「嘘」はキャラクターのNEEDとWANTを生む
- なぜ「嘘」を信じるようになったのかを考える
はじめに・・・
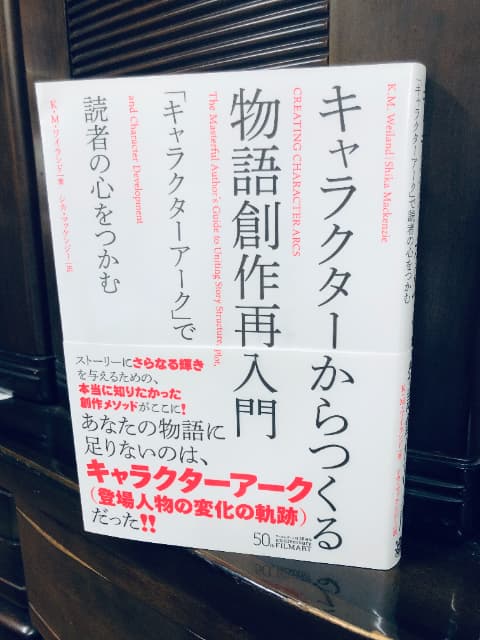
『キャラクターからつくる物語創作再入門』とは、キャラクターアークに焦点を当てて、キャラクターと物語構造の関係性や理解を深める一冊となっています。
※キャラクターアークとは、物語の中でキャラクターが経験する 内面的な変化や成長の軌跡 のこと。
キャラクターに、容姿・性格・特徴などをただひたすら追加しても、キャラクターが動くことはありません。
キャラクターアークへの理解が、読者の心をつかんで揺さぶるキャラクターを生み出し、最高の物語を作り出すのです。
物語を作るにおいて、「人物」と「プロット」に分けて考えていくのは大変危険です。
どちらかの要素をいい加減に設定すれば、物語全体がダメになる可能性があるのです。
それは、人物がプロットを動かし、プロットがキャラクターアークを作るという原理がそうさせているからです
逆に言えば、人物とプロットは一体化しているので、キャラクターアークがしっかりしていれば、
プロットも連動して安定したものになるということです。
本書はキャラクターアークに焦点を当てながら、
「ポジティブなアーク」
「フラットなアーク」
「ネガティブなアーク」
の3つのスタイルを言及しつつ、キャラクターとストーリー構成がいつどのように関係し合うのかを徹底的に掘り下げています。
キャラクターが信じ込んでいる嘘とは?
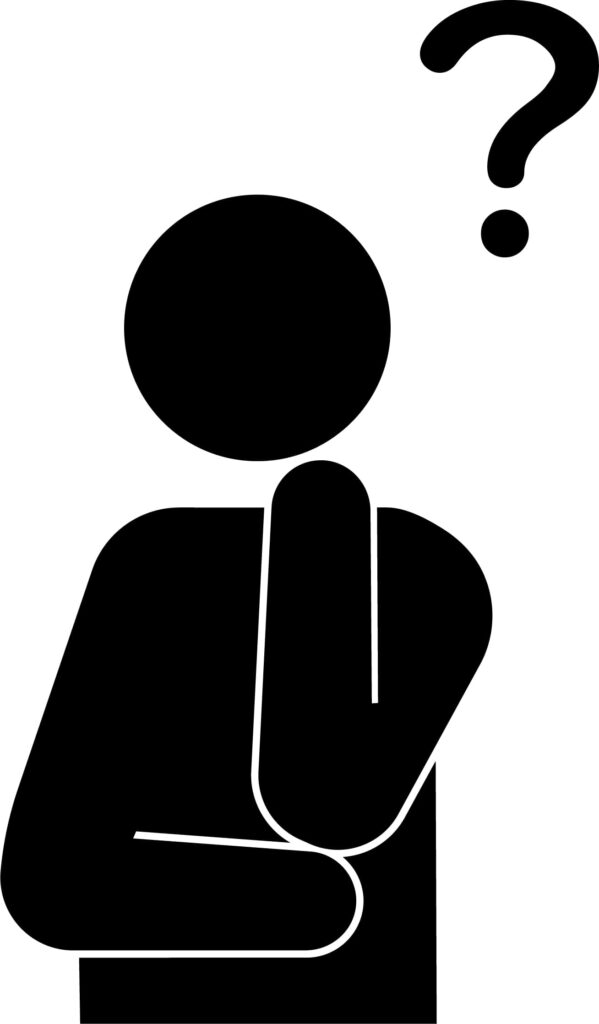
本書によると、アーク(内面的変化や成長)は、「キャラクターが信じ込んでいる嘘」をめぐって展開されていきます。
これがキャラクターの内面の未熟さという不完全さを生み出しており、自分や世界に対して間違った思い込みがある状態です。
例えば、「嘘をついてはいけないんだ!」と頑なに信じ込み、何でもかんでも正直に人に話してしまうキャラクターがいるとします。
このキャラクターは一見、何事もごまかさずに誠実に対応する人物に見えますが、「嘘をつけない状態」のために、会話の応用力が育たず不器用な会話しかできないのです。
当然、人を思った「優しい嘘」をつくこともできません。
ここでチャットGPTにも一例を考えてもらいましょう!

『キャラクターからつくる物語創作再入門』によると、アーク(内面的変化や成長)は、「キャラクターが信じ込んでいる嘘」をめぐって展開されていきます。これがキャラクターの内面の未熟さという不完全さを生み出しており、自分や世界に対して間違った思い込みがある状態です。
一つそのような嘘の例を考えてください。

では一つ例を考えてみます。
たとえば主人公が抱えている「嘘」は───
「人に頼るのは弱さの証だ」
この嘘によって、キャラクターは誰にも助けを求められず、自分だけでなんとかしようとします。結果として仲間との絆を深められず、孤立し、必要以上に傷ついたり限界を迎えたりします。
王道のバトル漫画やRPGにありそうな「嘘」設定ですね!
「嘘」はキャラクターのNEEDとWANTを生む

「嘘」を設定すると、キャラクターのNEEDとWANTという2つの相違を生み出します。
NEEDとはキャラクターが気づいていない真に手に入れるべきものであり、WANTとはキャラクターが表面的な解決のために手に入れたいと思っているものです。
キャラクターは常にゴールに向かって物語の中を動いています。
例えば、先ほどの「嘘をついてはいけないんだ!」と頑なに信じ込むキャラクターは、「正直者が一番正しい」という世界を目指していきます。
そのために、その「嘘」を信じるキャラクターに降りかかる困難を解決しようと試みていくのですが、それは全て表面的な解決にとどまり、これがWANTというわけです。
WANTを求めている間はいつまで経っても真の解決には至らないどころか、より嘘の沼に沈んでいくのです。
しかし、キャラクターの友人の「この世には優しい嘘っていうのもあるんだよ・・・」という言葉をきっかけに、実はは自分が間違っているのではないかと動揺します。
これがNEEDに触れるということです。
よって、表面的なWANTと深層のNEEDが混ざり合って調和し、新たな展開へと向かっていくのです。
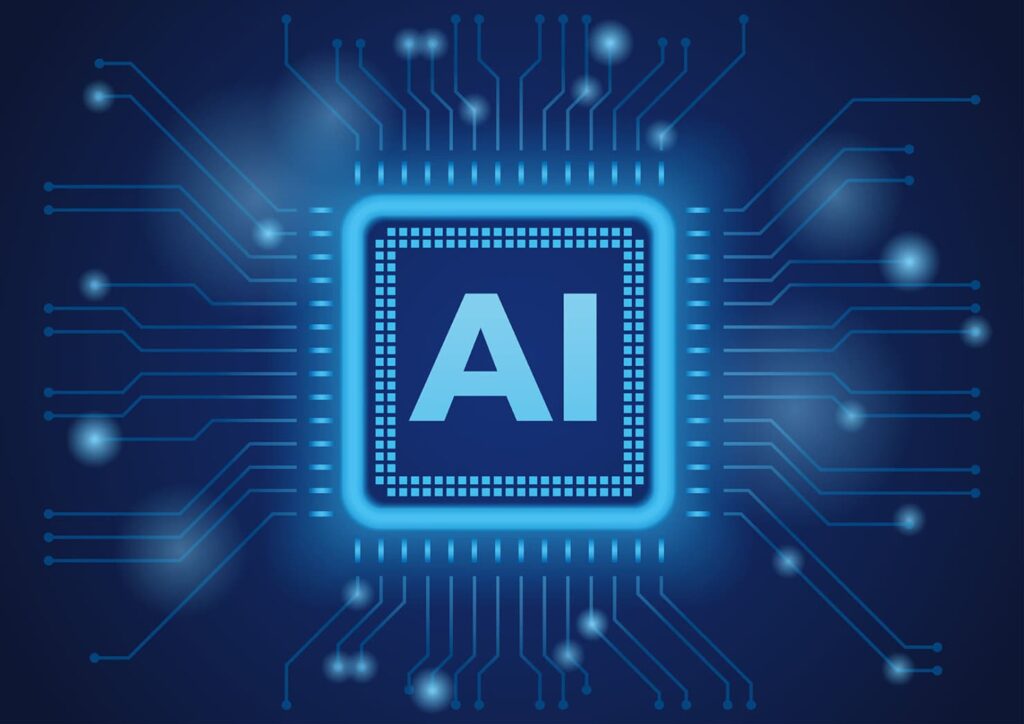
では、チャットGPTにも一例を考えてもらいましょうか!

先ほど考えてもらった嘘の例のNEEDとWANTを考えてください。
NEEDとはキャラクターが気づいていない真に手に入れるべきものであり、WANTとはキャラクターが表面的な解決のために手に入れたいと思っているものです。

なるほど、先ほどの「嘘(人に頼るのは弱さの証だ)」をもとに WANT と NEED を整理してみますね。
嘘:「人に頼るのは弱さの証だ」
●WANT(表面的に欲しているもの)
「誰の助けも借りずに、すべてを自分一人で成し遂げること」
→ 自立して強さを証明したい、弱さを見せないでいたい。
●NEED(本当に必要なもの)
「人に頼ることは信頼の証であり、絆によってこそ本当の強さが得られる」
→ 助けを受け入れ、仲間と協力し合うこと。孤立ではなく信頼によって成長すること。
つまり物語が進むにつれて、キャラクターは 「一人で成し遂げようとするWANT」から、「人と協力することで真に強くなるNEED」へ 変化していく流れになります。
この構造が、キャラクターのアークを自然に描く土台になります。
バトル漫画で一人で敵を倒すために突っ走ったキャラが、仲間に助けを求めてNEEDに目覚めるといったシーンが想像できますね!
なぜ「嘘」を信じるようになったのかを考える

嘘、WANT、NEEDの設定が終わったら、次はなぜ「嘘」を信じるようになったのかを考える必要があります。
このなぜ「嘘」を信じるようになったのかを、本書ではゴーストと呼んでいます。
ゴーストとは心の傷であり、ゴーストが大きいほど嘘もアークも大きくなります。
例えば、「嘘をついてはいけないんだ!」と思い込みを抱えたキャラクターは幼少期、昔気質な父親が信奉している薩摩教え(負けるな、嘘をつくな、弱い者をいじめるな)を叩き込まれます。
キャラクターは父親に一切逆らうことができず、その言葉を鵜呑みにせざるをえない状況でした。
その中でも特に嘘をつくことは最も父親を激怒させることで、それだけはどんな些細なことでも正直にならなければいけなかったのです。
そんな過去を持つキャラクターは、次第に「嘘をついてはいけないんだ!」と思い込むようになりました。
つまり、キャラクターのゴーストは、幼少期に父親に強制された薩摩教えが原因となります。
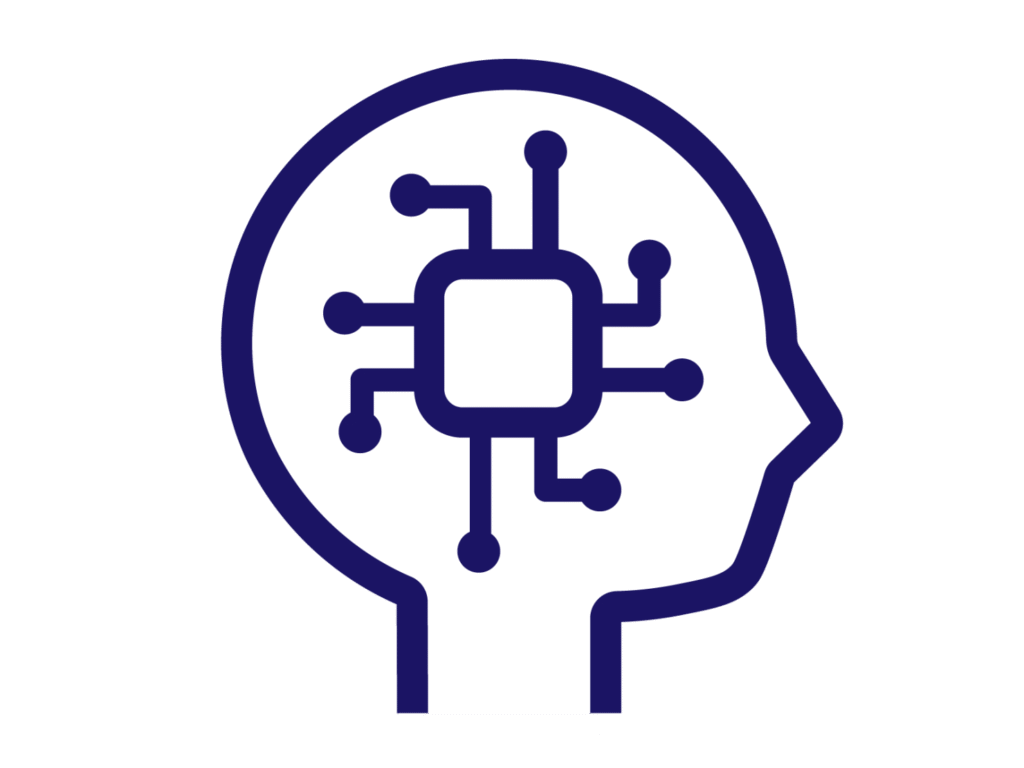
では、チャットGPTにも聞いてみます。

嘘、WANT、NEEDの設定が終わったら、次はなぜ「嘘」を信じるようになったのかを考える必要があります。
このなぜ「嘘」を信じるようになったのかを、ゴースト(心の傷)と呼びます。
先ほど考えてもらった例のゴーストを考えてください。

嘘を信じるようになった「きっかけ」「傷の源泉」=ゴーストを考えてみます。
嘘:「人に頼るのは弱さの証だ」
WANT:「誰の助けも借りずに、すべてを自分一人で成し遂げること」
NEED:「人に頼ることは信頼の証であり、絆によってこそ本当の強さが得られる」
ゴースト(なぜ嘘を信じるようになったのか)
幼い頃、キャラクターが大切にしていた人に頼ったことで、ひどく裏切られたり、失望させられたりした経験。
例1:子どもの頃に、親に助けを求めても「自分でやれ」と突き放され、心細さの中でやり遂げざるを得なかった。
例2:仲間に助けを頼んだが、裏切られたり置き去りにされ、危険にさらされた。
例3:失敗を人のせいにされた経験から、「人を信用すると傷つく」「助けを求めると弱さを突かれる」と心に刻んでしまった。
この「ゴースト」があるからこそ、キャラクターは 「もう二度と裏切られたくない」「弱さを見せて傷つくくらいなら一人で頑張る」 という嘘を抱え込み、物語の始まりではその嘘にしがみついて生きています。
このゴーストが具体的であればあるほど、読者はキャラクターの嘘を理解し、「その嘘を乗り越えられるのか?」という興味を持ち続けられるんです。
例を3つも挙げてくれました!
これだけでもキャラクターの奥行きが生まれて面白いですよね!
「普通の世界」を描写する

これまで、嘘、WANT、NEED、ゴーストとやってきましたが、これらを使ってキャラクターの特徴を見出し、読者を惹きつける必要があります。
その特徴を見出すためには、それを表現するための場所「普通の世界」が必要です。
「普通の世界」とは、キャラクターが「嘘」を信じやすい世界のことです。
キャラクターにとっては、その「嘘」が簡単にまかり通りますが、次第にそれが通用しなくなっていく展開になるような世界ですね。
例えば、嘘をつかずに正直者が褒められる世界があるとします。
小学生のキャラクターは、割ってはいけない学校の備品を誤って割ってしまい、怖い先生に怒られそうになり、周りにいた生徒も戦々恐々とするシーンです。
そんな中、キャラクターの「嘘をついてはいけないんだ!」という思い込みから潔く失敗を認め、それがプラスに働いたことから、逆に怖い先生に褒められる経験をします。
しかし、それはいつまでも続かず、学年が上がるに従ってそのバカ正直さが仇となっていきます。
そんなとき、同じ学年の女子生徒の兄が凶悪な事件に巻き込まれたことを、刑事である父親の会話を偶然聞いてしまいます。
ただ、女子生徒の両親はそのことを、女子生徒を思って明らかにしていませんでした。
にもかかわらず、キャラクターは教室でその女子生徒に正直に事件のことを話してしまうのです。
その直後、女子生徒は泣き叫び、教室にいる生徒の注目を浴び、幼馴染だった友人に胸ぐらを掴まれ、
「この世には優しい嘘っていうのもあるんだよ・・・」
と軽蔑された気持ちで言い放たれるのです。
その瞬間、キャラクターの「普通の世界」が壊れはじめ、WANTとNEEDが混ざり合って真の世界へと向かいます。

ではチャットGPTはどう表現するのでしょうか?

これまで、嘘、WANT、NEED、ゴーストとやってきましたが、これらを使ってキャラクターの特徴を見出し、読者を惹きつける必要があります。
その特徴を見出すためには、それを表現するための場所「普通の世界」が必要です。「普通の世界」とは、キャラクターが「嘘」を信じやすい世界のことです。
先ほど考えてもらった例の「普通の世界」を考えてください。

嘘・WANT・NEED・ゴーストを活かすには、キャラクターがその嘘を当たり前のように信じてしまう「普通の世界」を設定するのが重要です。
嘘「人に頼るのは弱さの証だ」
WANT「誰の助けも借りずに、すべてを自分一人で成し遂げること」
NEED「人に頼ることは信頼の証であり、絆によってこそ本当の強さが得られる」
ゴースト「過去に助けを求めた結果、裏切られたり突き放されたりして深く傷ついた経験」
普通の世界(嘘を信じやすい環境)
厳しい自己責任の文化:学校や職場、家庭が「自分のことは自分でやれ」「人を頼るのは甘えだ」という価値観で成り立っている。
成果主義の社会:成功や評価は「一人でできる強さ」によって決まるとされ、協力は「力不足の証」とみなされる。
孤立を美徳とする環境:家族も仲間も表立っては助け合わず、「弱音を吐かないこと」が尊敬される。
過去のゴーストを想起させる環境:人に頼ろうとした瞬間、笑われたり責められたりするような空気が漂っている。
この「普通の世界」にいることで、キャラクターは嘘を強化し続け、WANTにしがみつきます。物語が進むにつれて、この世界の価値観が揺らぎ、嘘を手放しNEEDにたどり着く…という流れが自然に作れます。
すごく殺伐とした冷たいイメージが伝わってきます!
そんな「普通の世界」を壊す暖かい仲間の絆というギャップは、さぞ読者の心を引きつけるのでしょうね!
まとめ

今回は、『キャラクターからつくる物語創作再入門』を微要約しつつ、チャットGPTの一例を見てきました。
- アーク(内面的変化や成長)は、「キャラクターが信じ込んでいる嘘」をめぐって展開される。
- 「嘘」を設定すると、キャラクターのNEEDとWANTという2つの相違を生み出す。
- キャラクターの特徴を見出すためには、それを表現するための場所「普通の世界」が必要
今回要約した箇所は、本書のほんの一部に過ぎませんが、それでも結構有益な情報だったりします。
シナリオを書く人じゃなくても、この本を読めば普段見ているドラマや小説がより一層楽しめるかもしれません!
最後までお読みいただきありがとうございます!もしよければ「ブックマーク」していただけると嬉しいです!





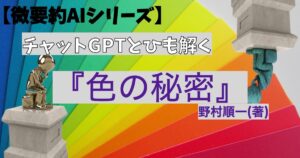

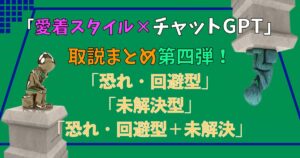
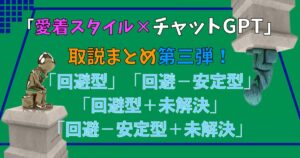
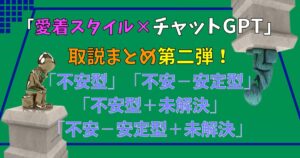
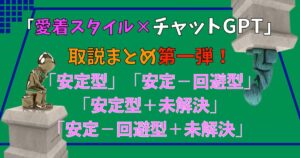

コメント