この記事は、『マンガでわかる ベンジャミン・グレアムの投資術』かぶ1000 (総監督)/ひげ羽扇(漫画)(standards ,2022/9/22)の一部をチャットGPTとひも解く内容となっています。

ベンジャミン・グレアムって知ってる?

知らねーよ!じゃああんた知ってんのか!

そんな怒らないでよ、わたしも知らないですよ・・・
- 「バリュー投資の父」投資家ベンジャミン・グレアムとは?
- ベンジャミン・グレアムの投資における4つの原則とは?
- 安全域とは?
はじめに・・・

『マンガでわかる ベンジャミン・グレアムの投資術』とは、バリュー投資の父とも称される世界的投資家ベンジャミン・グレアムの人生をたどりながら、その投資哲学や手法を漫画で学んでいく内容となっています。
グレアムの幼少期から熟年期までの漫画は、当時の時代背景や流れを踏まえつつグレアムの投資人生が描かれています。
また、各漫画の回ごとに続く解説ページは、グレアムの思想や思考パターンをなぞりつつ、詳しい投資手法が解説されています。
漫画といえど侮ってはならないといえるほど、かなり深く詳しい内容が述べられており、投資の歴史を味わいながら投資を学べる意義深い一冊となっています。
「バリュー投資の父」投資家ベンジャミン・グレアムとは?

主に1920年代後半から1950年代にかけて活躍した「バリュー投資の父」投資家ベンジャミン・グレアムとは一体何者なのでしょうか?
彼は、今日のバリュー投資の基盤を築いた男です。
バリュー投資とは、「企業の本来の価値(内在価値)に比べて割安に放置されている株を買い、長期的にその価値が市場に認められるのを待つ投資手法」のことです。
要は誰も気づいてない価値を持った株を手に入れて、成長するまで待つという方法。
その反対の概念が、グロース投資です。
実は、グレアム氏の弟子があの世界的なウォーレン・バフェット!
※ウォーレン・バフェットとは、長期にわたって市場平均を超える成績を残した伝説的な投資家のこと。「オマハの賢人」とも呼ばれる。
グレアム氏がバリュー投資を理論化し、弟子のバフェット氏が実践して世界一の投資家と呼ばれるようになりました。
まさかグレアム氏が、よくテレビでニュースになるウォーレン・バフェットの師匠だとは思いませんでした・・・
ベンジャミン・グレアムの投資における4つの原則とは?

ベンジャミン・グレアムの投資における4つの原則とは、以下のものを指します。
この4つの原則を心に留めてシンプルに考えれば、大きな利益獲得も夢ではないとのことですが、チャットGPTに聞いてみましょう。

ベンジャミン・グレアムの投資における4つの原則
①自分が何をしているのかを知れ
②決して自分の事業を他人任せにしてならない
③投機的行為には手を出してはならない
④自分の知識や技術に勇気をもって従うべきだ
があり、この原則を心に留めてシンプルに考えれば、大きな利益獲得も夢ではないらしいとのことです。
それはなぜなのか?そして、各項目ごとの意味と一緒に教えてください。

いい質問ですね!
ベンジャミン・グレアムは「バリュー投資の父」と呼ばれ、ウォーレン・バフェットをはじめ多くの投資家に影響を与えました。彼の投資原則は一見シンプルですが、投資家心理の落とし穴を避け、長期的に資産を守り増やすための土台になっています。
ご提示の4つの原則について、それがなぜ「大きな利益獲得も夢ではない」につながるのか、そして各項目の意味を解説します。
① 自分が何をしているのかを知れ
意味:投資対象の企業や仕組みを理解していなければならないということです。流行や噂に流されて「何となく買う」のは投機であり、博打と同じ。数字(財務諸表)、事業の内容、将来の収益性などをきちんと調べ、自分の理解できる範囲で投資することを重視しています。
なぜ利益につながるか:理解できないものに投資すると、相場の変動で不安になり、安いときに手放してしまいがちです。逆に理解していれば、適正価値より安ければ「今はチャンス」と判断でき、合理的な投資判断を継続できます。
② 決して自分の事業を他人任せにしてはならない
意味:投資は自分の資産を使った「自分の事業」だという意識を持て、ということ。証券会社、アナリスト、評論家に盲目的に従ってはいけません。最終的な意思決定は自分の責任で行うべきだという戒めです。
なぜ利益につながるか:人任せにすると、情報が偏ったり売買のタイミングを誤ったりします。自分で責任を持って判断することで「大衆心理に巻き込まれずに投資する姿勢」が確立され、長期的な利益を積み重ねやすくなります。
③ 投機的行為には手を出してはならない
意味:短期的な値動きやギャンブル的な「当てもの」を狙う投機は禁止、ということ。投資は本来、資産が将来生む価値を見積もって買う行為であり、値動きそのものを狙うのは危険だと説いています。
なぜ利益につながるか:投機は一時的に儲かっても、長期的には負ける可能性が高い。反対に、企業の本源的な価値(利益や資産)に基づいて投資すれば、時間を味方につけて利益を積み上げられます。
※投機:短期間の株価の上下や為替の動きに乗って売買し、差益を狙う。価値そのものではなく、「相場の変動」や「他人の心理」に賭ける行為のこと。
④ 自分の知識や技術に勇気をもって従うべきだ
意味:学んだ知識や分析の結果に自信を持ち、相場の一時的な上下や周囲の意見に惑わされず行動せよ、ということ。つまり「合理的な信念を貫く勇気」が大事という意味です。
なぜ利益につながるか:株式市場では短期的に価格が乱高下しますが、本質的な価値は急に変わりません。自分の分析に基づいて「割安」と判断したら、周囲が悲観していても勇気を持って買い、逆に過熱していたら売ることができます。これが市場の歪みを利用して利益を得る方法です。
まとめ
グレアムの4原則は、
「自分で理解する」
「責任を持つ」
「投機に走らない」
「信念を持って貫く」
というシンプルですが極めて普遍的なルールです。
これを守れば、大衆心理に振り回されずに「安く買って高く売る」ことが可能になり、長期的に大きな利益獲得につながるのです。
つまり、この4つの原則はより合理的に投資を続けるための、自分の心のブレを少なくするための思考法でした!
投資をやっていると「みんなはこうだ!」といった大衆心理に流されがちになって、いつしか「誰が正しいのか?」という他力本願になってしまうのです。
「投機は一時的に儲かっても、長期的には負ける可能性が高い」
この言葉は胸に刻むべきだと思いました。
本質的な価値を見極めたものが勝つ・・・
安全域とは?

安全域とは、「株や債券などを『本来の価値(内在価値)』よりも十分に安い価格で買うことで、見積もりの誤差や予期せぬ出来事があってもリスクを最小限に抑える」という考え方です。
この安全息を最初に投資の世界に体系的に導入したのは、ベンジャミン・グレアムなのですが、詳しく解説していきます。
チャットGPTが!

「株や債券などを『本来の価値(内在価値)』よりも十分に安い価格で買うことで、見積もりの誤差や予期せぬ出来事があってもリスクを最小限に抑える」という安全域をわかりやすく説明してください。

わかりやすく言うと、「安全域」とは 買い物で“お買い得”を狙うのと同じ考え方 です。
たとえば、本来なら1万円の価値がある商品があるとします。
でも、今はセールで7,000円で売られている。
このときに買えば、もし計算違いで実はその商品の本当の価値が9,000円だったとしても、まだ安く買えているので損をしにくいです。逆に、急にちょっと壊れたり需要が下がったとしても、1万円で買った人よりはずっと安全です。
投資でも同じで、株や債券の「本来の価値」を見積もり、それより十分に安い価格で買っておけば、多少の誤差や不測の事態があってもリスクを減らすことができる、という仕組みです。
つまり「安全域」とは、
👉 “価値より安く買うことで、余裕(クッション)を持たせてリスクを小さくする仕組み” です。
本来の価値よりも安く買っておくことで、何かあった時に損害を少なくするのが安全域という意味でした。
では投資における実際の安全域とはどのような方法で導き出すのか?
本書では、安全域の計算は2種類とされています。
一つは、「優良社債の利率」と「株式の収益率」を比較する方法、もう一つが、企業の「簿価」(帳簿上の価格)と「市場での価格(時価総額や株価)」を比較する方法です。
なんか難しそうですが、以下で解説していきます。
安全域①(「優良社債の利率」と「株式の収益率」の比較)

はじめに、安全域①(「優良社債の利率」と「株式の収益率」の比較)について解説していきます。
まずは、「優良社債の利率」と「株式の収益率」の意味をチェックしてみましょう。
企業が社債を発行しているとして、例えば額面100万円の社債で利率5%なら、1年間で5万円の利息がもらえます。
よって、優良社債の利率5%ということになります。
例えば、100万円で株を買って1年後に配当や値上がりで105万円になったら、株式の収益率は5%です。
グレアムは1965年当時の平均的な安全域を、「平均株価のPER」と「優良社債の利回り」を使って計算しています。
優良社債の利回りは、アメリカで一般的に流通していた「格付けの高い大企業の社債」の平均的な利回りのことですが、「平均株価のPER」とはなんのことでしょうか?
平均株価のPER

例えば、1965年当時の平均株価のPERは9倍だったので、その市場全体が1年間に稼ぐ利益の9年分の価格で株を買っていることになります。
もし企業の1株あたり純利益(EPS)が100円なら、株価は 100円 × 9 = 900円。
EPSが200円なら、株価は 200円 × 9 = 1,800円。
つまり、株価は純利益の9倍の水準についているということです。
純利益(EPS)が100円?それだけしか稼いでないの?どうしてその金額なのと思われた方もいると思います。
EPSは純利益÷発行済株式数で割り出せます。
つまり、ある会社が1年間で純利益100億円 を出し、発行済株式数が1億株 だとしたら、100億円÷1億株=100円(1株につき100円の利益を稼いだ)となります。
「1株につき100円の利益を稼いだというのは、利益を生み出しているのは会社であって、株ではないじゃないか!」と思われる方もいると思いますが、単に便宜的な表現です。
よって、平均株価のPERが9倍ということは、市場全体の株価が市場全体が1年間に稼ぐ利益の9倍の価格で取引されているということです。
益周り

さて、1965年当時の優良社債の利率は4%、平均株価のPERは9倍ということですが、平均株価のPERは9倍のままでは比較できません。利率で揃えてあげる必要があります。
これを解決するのが「益周り」です。
益周りとは、現在の株価で株を買うと何%の利益を得られるかを意味する数字のこと。(1株あたり純利益÷株価×100で計算)
PERから益周りを計算すると、1÷9×100=約11.1%となります。
安全域の計算

このことから、優良社債の利率は4%、株式の収益率約11.1%となりますので、その差約7.1%が安全域となります。
つまり、「もし利益がマイナス7%になったとしても、安全域内なので損失は発生しない」だろうということになります。
簡単にまとめますね。
- 優良社債はほぼ確実に会社が支払うことができる、一番安定した判断材料です。
- 株価は会社の利益を反映するので、利益に比べて株価が低い割安株となります。
- PERが小さい(株価が低い)ほど、利益に対して支払う価格が少ないです(PERが低い(株価が利益に比べて安い) ほど 益回りが高くなるので。株式益回り = 1 ÷ PER × 100)。
- もし、会社の利益が予想より減ったとします。
- PERが高い株(割高株)だと、利益減少で株価は大きく下がる可能性があります。PERが低い株(割安株)だと、株価はもともと低いので、同じ利益減少でも下げ幅が小さく済む可能性が高いです。
- 安全域 = 株式益回り − 優良社債利回りなので、安全域が大きい → 株価は十分に低く、利益が想定より減っても社債利回りレベルの収益は確保できそうという余裕があるのです。
- 先の例で、もし利益が7%減少しても、株式益回りはまだ 4%=社債並みの安全な水準に残る。つまり、損失を吸収できる余裕がある、という意味になります。
あくまで安全域は、「どの株買おうかな?より赤字がでない株を買いたいな」の指標ということです。
安全域②(企業の「簿価」と「市場での価格」の比較)
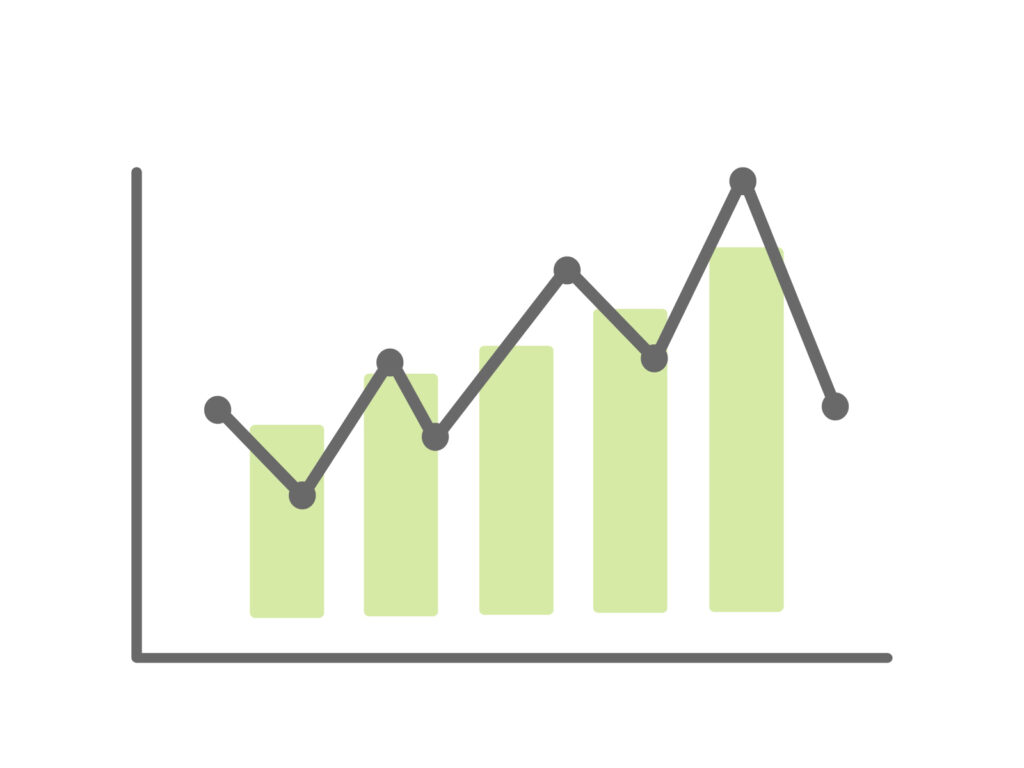
続いて、安全域②(企業の「簿価」と「市場での価格」の比較)について解説していきます。
まずは、「簿価」と「市場での価格」の意味をチェックしてみましょう。
簿価は会計上の価値、市場価格は現実に売買される価値ということですね。
グレアムは簿価(帳簿上の価格)と市場での価格(時価総額や株価)を比較して、時価が低ければ安全域が広いと考えました。

グレアムは簿価(帳簿上の価格)と市場での価格(時価総額や株価)を比較して、時価が低ければ安全域が広いと考えたそうですが、簡単にわかりやすく説明お願いします。

はい、簡単にわかりやすく説明します。
簡単な例
- 会社の簿価:1株あたり1000円
- 株価:1株あたり600円
この場合、株価は簿価より40%低いので、もし経営が少し悪化しても資産の裏付けがあるため損失が限定されます。これが安全域が広い状態です。
要するに、「本来の価値より安く買える株は、リスクが少なくなる」という考え方です。
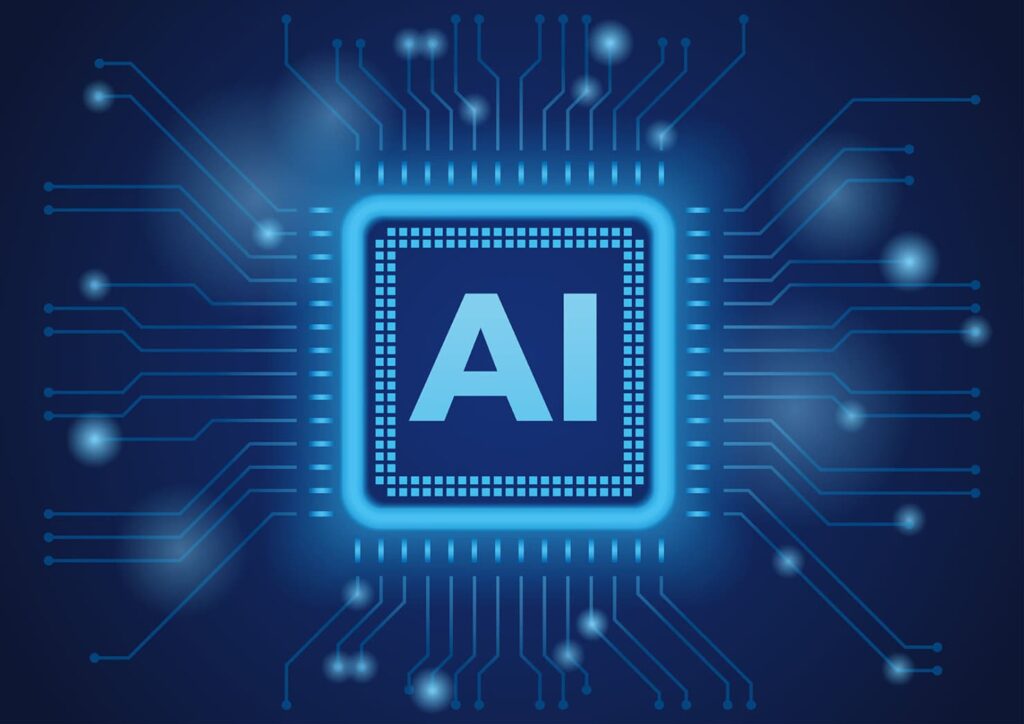
まだピンとこない人のために、さらに質問を投げかけてみましょう。

この場合、株価は簿価より40%低いので、もし経営が少し悪化しても資産の裏付けがあるため損失が限定されます。 この感覚について詳しく。

なるほど、その「感覚」がピンとこないということですね。
では、もっと身近な例に置き換えてみます。
あなたが中古の自転車を買うとします。
自転車の部品やフレーム、タイヤを全部新品で買ったら 10万円 かかる
でも実際に中古市場では 6万円 で売られている
この場合、もし買った自転車がちょっと故障しても、最悪パーツを全部交換しても10万円までしか損しませんよね。
つまり、元の価値(簿価)よりずっと安く買えているので、リスクが少ないということです。
株の場合
会社も同じように考えます。
簿価:会社の資産の「元の値段」
株価:市場での値段
会社Aの状況を考えます。
- 会社が持っている現金や工場や土地などの価値(簿価):100億円
- 発行している株の数:1億株
- 1株あたりの簿価=100億円 ÷ 1億株 = 100円
一方、市場での株価は60円とします。
- そのため、株価が仮に50円に下がっても、資産価値(簿価)が裏付けになっているので、損失は限定的
- 株を60円で買った → 会社の資産価値(100円)よりずっと安く買えている
- もし会社の業績が少し悪化しても、会社にはまだ土地や工場、現金が残っている
ポイントは、株価=損する可能性の値段 ではなく、株価<資産価値 なら、最悪の場合でも資産の裏付けで守られる、という感覚です。
株価が簿価より高い状態であれば、市場は「会社は将来もっと儲かるはず」と期待して株価を高めに評価しています。
この期待が業績が悪化して裏切られれば、「マジかよこの会社ダメじゃん。もうこの株手放そう」となる人が増えて、株価は期待分を大きく調整して下落します。
逆に株価が簿価より低い状態であれば、市場はすでに会社のリスクを織り込んで割安評価しています。
少し業績が悪化しても、「会社にはまだ資産が残っている」という裏付けがあるので、株価は大きく下がりにくいというわけです。
大きな期待が込められた簿価より高い株を買えば、何かあった時の下落幅は期待の分の価格が消えて、大きく下がるが、簿価より低い株ならそもそも期待してないので、何かあっても下がらない。
もし会社が経営破綻した場合でも、資産を売却して債務を返済したあと、残ったお金は株主に分配されるので、資産を全部売却し債務を返済して残った金額が株主に分配さる。
この場合でも、簿価より高い株価の場合はもちろん簿価の金額で資産が売却されるので、確実に超過分は損するが、簿価より低ければ、純粋に資産を売却して債務を返済したあとに残ったお金分の損しかない。
このような安全域を駆使して、グレアムは投資を行っていたということですね。
まとめ

今回は、『マンガでわかる ベンジャミン・グレアムの投資術』の4つの原則や安全域などを解説してきました。
- ベンジャミン・グレアムとは、今日のバリュー投資の基盤を築いたウォーレン・バフェットの師匠。
- ベンジャミン・グレアムの4つの原則とは、①自分が何をしているのかを知れ②決して自分の事業を他人任せにしてならない③投機的行為には手を出してはならない④自分の知識や技術に勇気をもって従うべきだ。
- 安全域とは、「株や債券などを『本来の価値(内在価値)』よりも十分に安い価格で買うことで、見積もりの誤差や予期せぬ出来事があってもリスクを最小限に抑える」という考え方のこと。
今回の解説は本書のほんの一部ですが、しっかり理解しようと思うととんでもない分量になってしまいますね^^;
少しでも投資に興味がでたら、ぜひ本書をおすすめいたします。
最後までお読みいただきありがとうございます!もしよければブックマークしていただけると嬉しいです!

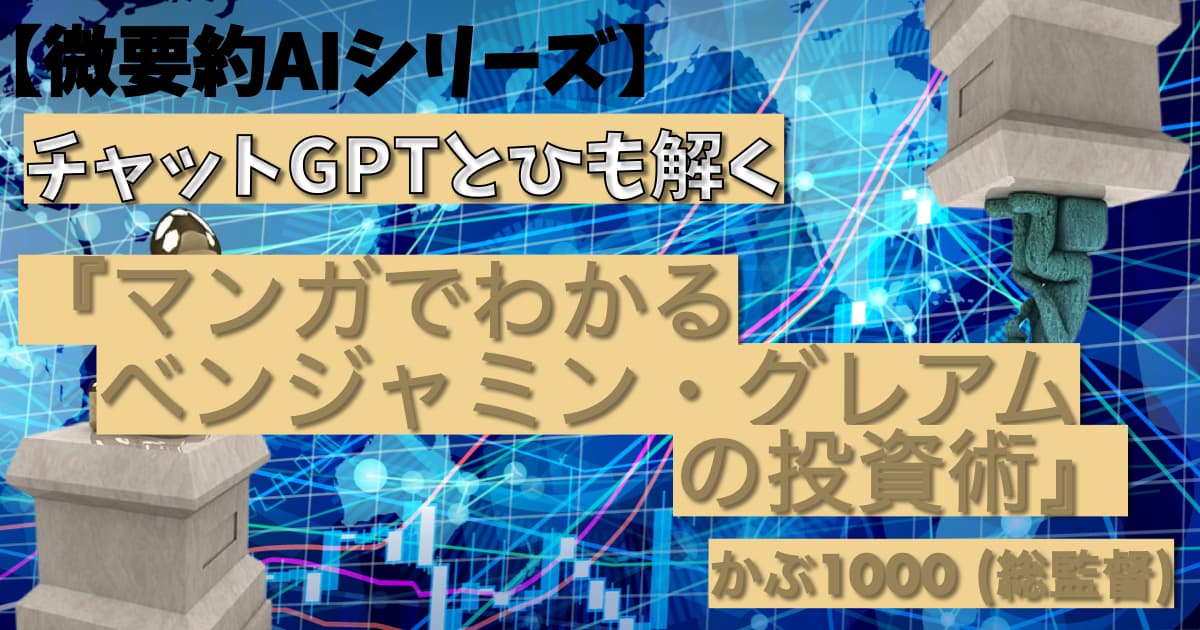



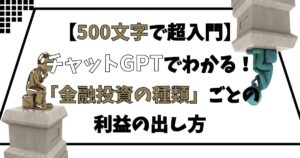
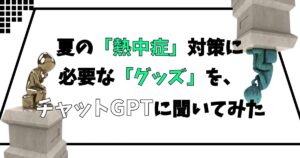
コメント